|
「あ、もしもし、翼?」
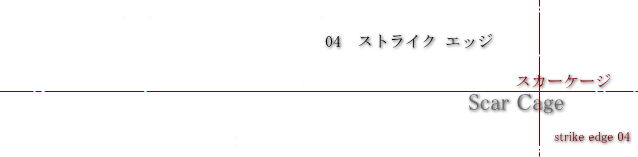
「よう、いらっしゃい」
インターフォンに出たのは翼だったけど、玄関で俺たちを出迎えたのは柾輝だった。
「スリッパ要る?」
おまけに他人の家なのに、何の躊躇いもなしに作り付けの棚を開けてしまう。俺は思いっきし呆れながら踵を使って横着に靴を脱ぐ。
「いらね。お前だって裸足じゃん」
「いや、サン、お客さんだし」
「お前も客だろが」
俺が突っ込むと柾輝は軽く笑って開けた扉を元へと戻す。それからこっちだというように顎で小さく合図して、迷いのない足取りで階段へと脚を向ける。
なんだかなぁ、よっぽど入り浸っているのか、他所ん家なのに物凄いこの家に馴染んでるよ、こいつ。
翼んとこの両親、何にも云わねぇのかなぁ、この前といい今日といい、お母さんの姿すら全然見ねえけど。そういや翼んとこの親って何やってんだろ、デカイ家の割には人の気配があんまりないし。この前だって明け方近くに総勢八人がばたばたがたがた騒いでりゃ普通は怒られそうなもんだけどなぁ。
内心不思議に思いつつ、俺は一応お邪魔しま〜すと断りを入れてから玄関マットに脚をのせた。
寿樹もパソコンは持っているが、なにやら寿樹のヤツじゃ件の品は見れないらしい(この辺俺はよく解らん)。翼に連絡したら翼のヤツなら大丈夫らしいので、かくして俺たちは急遽予定を変更して武蔵森駅を通り過ぎたその先の翼の家にやってきた。
翼の家は外から見ると明らかに普通の家の二軒分は在りそうなデカさだが、やっぱり内部も普通の家じゃありえないほど広い。階段の幅も民家じゃありえないほど広くて、俺と寿樹が並んで上れるぐらいだ。
征輝の背中に続いて階段を上りながら、隣の寿樹が下げているコンビニのビニル袋に俺はちらりと視線を流す。
ペットボトルとスナック菓子の隙間に無理矢理突っ込まれた透明ケース。その中に収められたディスク。
おそらくそこには俺にとって苦い記憶が詰まってる。
そもそもあんな奴らに拉致られた時点で既に人生の汚点、超特大黒星以外の何物でもない。どこからどこまで映っているのか知らないが、どう転んでも反吐が出そうに素敵な青春のメモリーであることに間違いない。確認なんかしねーでバキバキにへし折って川に向かってぶん投げちまいたいのも山々だが、捨てられない訳が在る。
ビデオを撮られたことは忘れていたが、忘れられない奴はいた。
ジョーイ。
あの妙な空気を持つ男。
ふとした瞬間、俺は通りすがる薄暗い路地裏の影にアイツの姿を探してる。
別にジョーイに復讐しようとかそんなつもりはない。見つけ出してそれでどうするのか俺自身解っていない。
けれど、それでも俺はあいつに会わねばならない、何故だか強くそう思う。
だからどれだけ胸クソ悪い映像が詰まっていようとこのディスクは捨てられない。これは俺が初めて手にした奴へと繋がる細い糸だ。
ただしジョーイは神出鬼没だって下っ端が云っていた。もしこの中の映像に奴の居所を示す何らかの手がかりが在ったとしても、明日にはもう奴は姿を消しているかもしれない。それどころか既に手がかりが役に立たない情報になってる可能性すらある。どちらにしろ俺は急ぐべきだろう。
だから、仕方がないんだ、と俺は自分に云い聞かせる。
確かに隠すような鞄はなかった。こんなの安良木のとこに持ってけない。けど、どうしても安良木のとこに向かいたいのなら駅のコインロッカーにしまうって手もあった。行こうと思えば行けた。いくらだって手段はあった。
それを、掴みかけたジョーイのシッポのことで頭がいっぱいの状態で会うのも失礼だよな、俺はバカだから顔に出ちまうしバレたら余計な心配かけるかもしれないからよくないよな、って俺はさっきから自分の行動を正当化しようと何度も何度も自分に云い訳している。
俺のこの後ろ暗さの原因は、もちろん安良木よりも自分の都合を優先させちまった所為もある。だけどそれ以上に、痛いぐらいに不安で心配で堪らなくて無事な姿が確認したいのと同時に、顔を合わせずらい気持ちが心臓の一番底の部分に隠れていて、今日見舞いに行かないですんだことにほっとしている俺が居るからだ。
俺の不安と心配のそもそもの元凶である住所や嘔吐、そしてあの忌まわしい窓の格子のこと、それら全ては安良木が自ら進んで『俺だから』話してくれたことじゃない、俺は棚から牡丹餅みたいな偶然によって知ってしまったに過ぎない。そんなふうに安良木の意思とは無関係な経緯で、勝手に土足で彼女の秘密に踏み入ってしまったことを俺は申し訳なく思っていた。
だって、安良木は誰にも知られたくなかったのかもしれないじゃないか。
今まで黙っていたし、何より笑って話せるような内容じゃない。もしかして、偶発的に知っただけの住所にのこのこ見舞いに行ったりしたら嫌な顔されるんじゃないか、迷惑なんじゃないかって、俺は安良木に疎まれてしまうことが恐かった。
安良木が好きだからこそ、俺は安良木に嫌われるようなことはしたくない。
好きだから会いに行きたいのも、好きだから会いに行きたくないのも、どっちも本当の気持ちだ。
それがディスクの出現によって、俺の心の天秤は会いに行きたくないへと傾きを変えてしまった。
いざ不測の事態によって顔を合わせることを明日に先送りするだけの理由を手に入れてみれば、俺は手のひらを返したように行かなくて済んだことに安堵感を覚えている。最低だ。あんなに安良木は辛そうだったのに、あんなに安良木を心配していたくせに、俺は今自分が傷ついたり嫌な思いしなくて済んだことに安心している。
ごめんな、ラギ。
明日こそ覚悟を決めて会いに行くから。
「なぁ、そういえばお前昨日どうしてたの?」
俺はウジウジした思いを断ち切る為に、前を歩く征輝に向かってふと思いついたことを口にしてみる。昨日の翼の意味ありげな『あいつもいろいろ多忙な身なんだよ』ってにやにや笑いの理由が俺には解らなかったから。
俺の言葉に柾輝が肩越しににやっと笑う。
「何?サン、俺が居なくて寂しかったわけ?」
アホか。
俺はケッと鼻の辺りに皺を寄せる。
「バッカじゃねぇ?世間話だろ、こんなの。ナルだったのかよ、お前」
「あはは〜そうだよね〜自意識過剰だよね〜」
「ハハッ、須釜サン笑いながら睨むなよ、冗談だろ?」
「笑ってませんよ〜睨んでるんです〜」
階段をテンポ良く上がって行く柾輝の背中が僅かに揺れ、くくっと喉の奥で笑ったような声が微かに漏れ聴こえる。
「悪かったって。でも、誓って俺は二股かけるような下衆野郎じゃないから、アンタにとっちゃ無害な存在のはずだぜ?」
え?何?
ちょっと待てよ?
ということは何か?
こいつも彼女持ちか?
「翼、来たぜ」
俺が何か云うより先に、さっさと柾輝は翼の部屋へと入っていってしまう。小指一本分ほど開きかけてた唇に空気を喰わせただけで、俺は結局口を噤んでその後へと続く。
だが、その背をついつい訝る様に見詰めてしまった。
だってなあ、柾輝も相当な曲者だぞ、いったいこいつと付き合う女ってどんなだ?
確か前に好きでもねぇ女と付き合う奴の気が知れねえとか云って、サルにスゲエ罵られてたよな。これだからモテるヤツはとか僻みモード全開でサルがブツブツブツブツえらい呟いてたけど、まあ征輝がモテるっつーのは寿樹がモテるという時空が捩れているとしか思えない事実に比べれば全然納得できる。
いいガタイしてんし、顔も普通にかっこいいし、性格もいいよな。女相手だからって露骨に態度を変えたりするとかじゃなくて、こいつはなんでもない顔でさらっと優しくしたりするしなあ。
モテるよなぁ、絶対。でも、本当に好きな奴じゃないなら付き合うなんて面倒くさいことしたくないって云ってるような男だぞ、そういう奴が本気になる女ってどんなだよ?
想像つかねぇなあ、と俺は内心首を傾げつつ、翼の元へと歩み寄る。
「よ、いきなり電話して悪かったな」
相変わらずきちんと整頓されている例のだだっ広い部屋、翼はすでにパソコンの前に座っていた。その横から六助が何やら画面を覗き込んでいる。後の二人の姿はない。俺が電話した時、丁度選抜の練習からの帰り道だった所為だ。
俺が声を掛けると背中を捻るようにしてこっちを振り返る。練習後で少しばかり髪が乱れていたって翼様が麗しいのに今日も変わりはない。
「別に構わない、むしろ僕もあの時の状況には興味があるから誘ってくれてありがたいぐらいだよ。で、どれだ?」
俺は寿樹が口を広げてくれたビニル袋からディスクを取り出す。それをまず渡して、それから俺はピンクの花束を翼に差し出した。
「…、ちょっといいかな?」
残りのペットボトルと菓子を六助に渡していると翼の声が俺を呼ぶ。視線を戻すと、数枚のディスクと花束を手にした翼が大きな瞳を細めて艶やかに微笑んでいた。
「ディスクの方は解るけど、こっちのこれは何?」
「何って……見たまんまだけど?」
俺が首を傾げると、花を片手に翼の笑みはますます艶を増す。
だが、ごくごくさりげない動きを装って六助と征輝は俺から離れていく。
何だ?と思った瞬間、バラのようにお美しい翼様のお口から放たれたバラのように棘だらけのお言葉で漸く俺はその理由を悟った。
「お前馬鹿?どういうつもりで僕に花束なんか持ってきてるの?プロポーズ?だったら悪いけどお前みたいなじゃじゃ馬お断り、お前に本気で付き合ってたら僕の胃に穴が開くよ。そもそも僕がこんなの貰って喜ぶ訳がないって思わなかったの?それとも何?お前は僕が花を貰って喜ぶような男に見えるの?ふぅん、あっそう、一体俺のどこをどんなふうに観察した結果そういう結論に至ったのか是非聴かせて貰いたいねぇ」
ブリザードのような言葉と視線にやっとのことで翼様唯一の地雷原に脚を踏み入れかけてることを理解した俺は、メッソーもございませんと顔の前で左手をぶんぶん振り回す。
「いやホントはそれラギに買ったものなんです!みやげとして用意してたものだからつい渡しちゃっただけで、別に全く他意はありませんから!」
……正直云うとさっき翼の顔見たら何か似合う気がして、どうせ今日はもう見舞いも行かないからいっかーってついふら〜と翼に差し出しちゃったんだけどさ(云ったら漏れなくぶっ殺されることだろう。アイドル顔負けの超美少女ヅラも翼にとっちゃコンプレックスみてーだから)。
俺のあまりに必死な否定っぷりに(何しろ命がかかってる)気の弱い人なら目が合った瞬間土下座してしまいそうな、この世の物とは思えないほど刺々しい一瞥を寄越しただけでそれ以上の追求は勘弁してもらえた。
花束をキーボードの脇に置きながら、それでもまだ不機嫌そうに眉を顰めた翼が捻っていた上半身をパソコンへと戻す。
「だったら持って帰れよ、水切りしておけば明日までもつから。どうせ明日にでも行くんだろ?」
「そうなのか?」
背を向けてしまった翼の代わりに俺は隣の寿樹を振り仰ぐ。けど、寿樹もさあとでも云いたげに肩を竦めるジェスチャーをしてみせただけだ。
まあ、家に帰ればヒナコがいるから解るだろう。それにもし明日までもたなくたって、どの道俺はもうこの花束を安良木の元に届けるつもりは毛頭ない。見舞いの延期は花を買い換えるいいチャンスだっていうのも云い訳のひとつであって、明日また新しいのを買うことを既に俺は決めている。
翼の椅子がぎしっと鳴いた。ついで呆れたような吐息が続く。体重をかけることで背凭れを神経質そうに揺らしながら、心底軽蔑しているような声でディスクに書かれた文字を読み上げていく。
「無修正裏映像、ダイナマイトエロス、極上素人大集合、お宝映像美少女編、チーズケーキ、マニアッカーズ……非常にインテリジェンス溢れるセンスだね、残念だけど高尚過ぎて気が合いそうにない。おい、どれに入ってるんだ?」
俺は再び寿樹を振り仰いだ。
寿樹は今度は軽く顎に手をやりながらちょっと考える素振りを見せる。
「まあ、彼の口振りとその分類名から察するに、お宝映像美少女編か極上素人だと思うけど〜。どっちかっていうと美少女のが確率高いかな〜」
「んじゃ、とりあえず美少女頼む」
翼がディスクをパソコンに入れる。
「どれだ?」
ういーんというモーター音の数秒後、画面上にはパソコンに不慣れな俺じゃ目がチカチカしそうなちっこい文字がずらーっと出現した。
…オイオイ、これ全部アイツ一人で集めたエロ映像なのかよ。
いや、気持ちは分かるよ、俺だって男のときはかなりの数のエロ本やエロビにイロイロお世話になったもん。だから、解るよ、解るけどでもなぁ、なんつーか、こう、他人のオカズを冷静に検分すんのってやるせねえよなぁ。ほんと気持ちは解るんだけどさあ、でもあの明らかに非モテの兄ちゃんが必死こいて集めてたんだと思うと、自分のことは棚上げにしてイタイ通り越して何かもうせつねえよ。
『えっちなお年頃』とか『おしゃぶり大好き』とか、上の方を読んだだけで俺はげんなりしてきて首を振った。
「わかんね…あっ、ちょっと待って、手錠の子とか手錠のナントカっていうのあるか?」
アイツは俺のこと手錠の子だって呼んだ。だからもしかしたらって思ったんだ。
画面の文字が上に向かって動き始めて、すぐに止まった。
「あるぞ、『手錠のお姫様』」
アホか、と突っ込みたかったが、それどころじゃない。俺は翼の椅子の背凭れを握り締め、身を乗り出した。
「見せてくれ」
かちかちっという音に続いて画面が切り換わる。
画面いっぱいに広がるグレイ。その中央。
俺は舌打ちした。
「ビンゴだ」
映し出された映像に、予想通り俺の胸には何ともいえない苦い思いが広がった。
俺の背後のコンクリートのグレイは手錠で拘束されていた所為であの日見ることは叶わなかった色だ。
打ちっぱなしのその壁を背にして俺は首を垂れている。
カメラは鎖に繋がれた俺を真正面から捉えている。腹の立つことに俺のワンピースの皺がはっきり解るほど画像は鮮明だ。この分なら俺の情けねぇツラもきれいに映っていることだろう。
やがて俺は身じろぐ。緩慢な動きで首を擡げ、そして一瞬の間の後、文字通り表情を凍りつかせた。
ビビって狼狽してるのがバレバレのツラ。
やっぱりバッチリ映っていたその顔に、俺は思いっきり舌打ちしたいのをどうにか堪えた。
左手から人影が現れる。その顔にはモザイクがかかってたけど、俺にはそれが誰だか解る。卑怯にも自分のツラにだけモザイクいれやがった男の名は宍戸だ。
近寄ってくる宍戸に俺の表情はますます硬くなる。状況を考えれば仕方ないってのは慰めのようで慰めにならない。それを解っているのか、周りの奴は画面の俺をおちょくったり、下手な気休めを云ったりもしない。
「なあ」
発した声があまりにも尖っていたから自分でもビックリして、俺は慌てて云い直した。
「なあ音が出てないぜ?」
喋ってるはずの宍戸の声は聴こえない。翼がディスプレイへと手を伸ばす。何やら指を動かしていたが、それ以上無理なのか、指が止まったところで首を振った。
「駄目だな、最大にしても何も聴こえない。音が出てないんじゃない、初めから音が消されてるんだ。大方誰か仲間の名前でも口走っていたか、声自体残したくなかったんだろ」
「ふうん…」
音が出ないことに俺はがっかりして、アヒルみたいに唇を尖らした。
畜生、あいつらセコイ真似しやがって。確かにシドはジョーイに話しかけていたし、名前も呼び合っていた。俺はそういう会話の中に、もしかしたら俺が覚えてないだけで、ジョーイの居所を示すような重大なヒントをあいつら口走ってたんじゃないかって期待してたのに。
しょっぱなから出鼻を挫かれた思いでいっぱいの俺の視線の先、画面が一瞬乱れ、ワンピースのファスナーが下ろされる。
アレ?っと妙な違和感を感じる俺の背後で、六助がゲッっと変な声を上げた。その声に感電したみたいに突然画面から俺の姿が掻き消える。
「何だよ?どうしたんだよ」
「お前一人で見ろ。俺たちはあっちにいるから」
……あ〜ハイハイ、なるほど。
あれか、気ぃ使ってくれてんのか。まあ確かにこっから俺チチ丸出しだもんなぁ、普通の女ならそら嫌がるわな。
けど、生憎普通の女じゃない俺は早くも席を立とうとしていた翼を腕をかざすことで制した。
「俺は別に構わねぇよ、チチぐれーお前らに見られたってどってことねぇし」
「僕は僕以外の人がの半裸を見るなんて言語道断だと思うんだけどね〜」
「ウルセエよバカ。つうかお前だけはあっち行けよエロジジイ」
俺は寿樹のアホを肩でぐいぐい押して退かせようと試みたが、もちろんこのエロジジイが素直に従う訳がない。
「お前が構わないなら見せてもらうけど、本当にいいのか?僕はパソコン使わしてやるぐらいで恩に着せるようなセコイ男じゃないから、無理する必要なんかないんだぜ?」
てゆーか、寿樹の奴、俺が全力で押してもびくともしねえでやんの。俺は首だけは翼に向けながら、ちょっと意地になって相撲の稽古みたいに両手でその胸に手を突いて押してみる。
「だから別にいいってぇ〜っメエ放せ!」
「やだなあ、から抱きついてきたくせに〜」
寿樹に捕まってジタバタもがいている俺に向かって、翼が呆れ果てたような溜息を吐く。再びパソコンに向き直った翼を見て寿樹のアホも俺を解放する(因みに体重かけて両手で突っ張ってみたのに寿樹はびくともしなかった。畜生、人を女にしといて、テメエばっかりすくすく成長しやがって、って俺が男だったときからこいつはデカかったか)。俺はさっきと同じように、一番画面がよく見える、翼の背後に陣取った。
「途中で気が変わったらすぐに云えよ。じゃあ、再開するぞ」
かちっという音と共に半裸の俺が再び出現した。
手錠に繋がれたままの俺の周囲にモザイク仮面の男どもが群がってくる。
全員が黙ってモニタに視線を注いでいる中、一分と経たない内に俺はちょっぴり別にチチくらいかまわねーよと云ってしまった自分の台詞を後悔し始めていた。
俺の中ではこの廃墟での記憶は生きるか死ぬかのガチンコの戦いでしかなくて、そんな状況で撮られたもんなんかチチが丸出しだろうがパンツ丸見えだろうが、どうせクソツマンネー映像だろって高をくくってたんだけど…………結構エロいぞ、コレ。
半裸っつー中途半端な脱ぎっぷりに手錠で拘束、そんでもって複数に囲まれて苛められてるプレイ(ホントは苛めなんて可愛いもんじゃなくあいつら本気で俺をレイプしようとしていた訳だが)というのは何気に男の嗜虐心をソソらないでもない。
内心俺は迂闊な己の発言にのた打ち回って背中に嫌な汗をかいていた訳だが、ふと、あまりにも俺がじたばた踊ってるだけの時間が長いことに気が付いた。それで漸く最初の違和感とやけに不自然に途切れることが多い訳にも合点が行く。
「なあ、これ、俺があいつらの仲間ぶっ倒したとこはカットされてんぞ。あと、一番最初の、剥かれる前にシドに殴られたとこも、あいつらに薬飲まされたとこもカットされてた」
「ああ、だからか〜。やけに動きがぶつぶつ途切れるなあって思ってたんだよね〜」
例によって寿樹は相変わらずの呑気な調子で返事をしたけど、他の奴らは黙ったまんまだ。
やがて例の火責めが始まった。手錠に繋がれた俺は必死に身を捩って炎から逃れる。
…………。
なんつーか、最早明らかに微妙な空気が場を支配していた。
無声のエロ映像を本人が居る前で見てんだもんな。俺が居なけりゃこいつらも口開くんだろうけど、流石に本人居る前じゃ何も云えねぇよなぁ。
翼は気が変わったら云えって云ってたけどさあ、やっぱり恥ずかしいから勘弁なって今更止める方が余計気まずくねぇ?
こうしてみると俺ってチチでかいんだなぁ。スゲエ揺れてんよ、ボインボイ〜ンってな、アハハ、ハハ……はあ……こりゃこいつらの今夜のオカズは決定だな…(遠い目)。
お前らも居た堪れないだろうが、こんなもん一緒に見ることを自ら進んで提案しちまった俺の方がもっと居た堪れないから我慢してくれ(まあ肉体的にはこいつらの方が居た堪れないことは間違いないが)。
「、ジョーイは映ってるのか?」
翼が画面を見たまま、感情を削ぎ落とした事務的な口調で尋ねてくる。
「いんや、さっきから全然映ってねえ。今金のジッポー持ってんのが俺が最初にフットサル場で鼻を折ったシドこと宍戸。あとの二人は知らねぇ」
俺がそう云ってる途中で唐突に映像は停止した。
「え?何?どうしたの?まさかこんだけ?」
画面上には顎を引き、ちょうどカメラ目線気味に何かを激しく睨み付けてる俺の顔。
ああ、きっとジョーイを見ているに違いない。この後、俺は宍戸の持ってるジッポーを農薬に蹴り込み、翼様にこっぴどいお叱りを受けた例の放火を引き起こすはずなんだけど。
「…駄目だな、これで終わりだ。手錠ってファイル名は……このディスクにはもうないな」
俺は忌々しさからついに舌打ちした。
くそう。
ジョーイのジョの字もなかったよ、畜生。
「おい、、この後もカメラを回されてたのか?」
「多分撮ってたはずだ。カメラ持ってた奴はリンチに加わらないでずっとカメラ構えてたから、少なくとも俺が火をつけるまでは絶対撮ってたと思う」
寿樹がデカイ身体を屈めてパソコンの画面を覗き込む。
「手錠のお姫様の更新日時は先月の二十六日だね〜。ちょっとごめんね、他は…この日に更新してるの、ないね」
「考えられる条件はそれぐらいだな、情報が少なすぎる。最終的には全部確認するにしても、手錠、日付で先に調べてみるか?どうせ全部調べたところで期待してるような結果なんて出るわけないと思うけど」
「うん、音声消したりこまめに編集したりしてるぐらいだから、僕もこれ以上何にもない方に一票って感じだけど、一応念の為お願いしてもいいかな?」
かちかちって音に続いて、かしゃんとディスクが出てきた。それを寿樹は流れるようにケースに収めて、別のディスクを翼に差し出す。それはいい。それはいいのだが、ケースにしまった最初のディスクを手から離す様子はない。
「……お前、なんでそれ持ったままなんだよ?」
「え?だって椎名君のところに忘れたら困るでしょ」
俺はめいっぱい広げた左手を寿樹に向かって真っ直ぐ突き出す。
「うん、そうだな、確かに忘れたら困るよな、でもお前がそんなにがっちり持ってる必要は全然ないよな、つうかよこせソレを」
寿樹がにっこり笑顔を浮かべて、普通の人じゃ手の届かない、自分の顔の横へとさり気なくディスクを移動させる。
「、結構すぐに物なくすじゃない。だから僕がの代わりに大事に保管し」
予想通りのその返答に、俺は台詞の途中でさっさと実力行使に出る。
この大嘘吐きの詭弁野郎め。俺に隠されないように今の内から確保してるってことも、手に入れた暁にはそれを何に使うつもりなのかもバレバレだっつーの!
俺の手のひらを胸を反らすことで躱しながら、寿樹はディスクを持った右腕をさらに天井に向かって伸ばす。
「よこせよ!テメエ何に使う気だソレ!」
「やだなぁ〜使うだなんて人聞き悪いな〜」
俺は寿樹の肩に飛びついて、どうにかそれを奪い取ろうと手を伸ばす。けど、あとちょっと、ってところで今度は左手にディスクが移動する。
「人聞きが悪いもクソもほんとのことだろうが!」
「ひどいな〜云いがかりだよ〜そんなことしないよ〜」
「そんな棒読みで誰が信じるか!」
俺は猿の様に寿樹の腰に脚を巻きつけ、奴の頭を踏み台にしてさらに手を伸ばす。すると今度は背中の方へとディスクが移動してしまう。
「てめー!ふざけんな!よこせ!」
ぎゃあぎゃあと争奪戦を繰り広げる俺らの背後では、翼たちが我関せずとばかりに俺たちを無視して黙々と作業を続けている。
「須釜サンってサンが絡むと途端にガキになるよな」
「ほっとけよ、それより次。エロスにはないぞ」
「人ん家なのになあ、あんなに暴れて。…ほい。なあ、チーズケーキって何だ?」
「さあ?…なんだ、他に比べてやけに少ないな…ここにも手錠って名前のつくやつはなし」
「一個開いてみろよ」
かちかちっという音の後。
『ぃ…っやぁあぁぁぁッ…!』
ついさっき音量を最大にしたスピーカー。
そこから吐き出されたのは悲痛な悲鳴だった。
寿樹の背中にぶら下がるような格好をしていたはずなのに、いつのまにか俺は翼の背後、パソコンの真ん前に突っ立っていた。
『…っやあっ、いやぁいたい、いたぁいやめてぇ!』
女の子の悲鳴は部屋中に響き渡っている。
でも、誰も何も云えなかった。
うるさいとか、ちっちゃくしろとか、そんな普通の反応をするだけの余裕がなかった。
テレビよりちっちゃいパソコンの画面。
そこに映されてるモノ。
中三にもなればアダルトビデオぐらい誰だって見たことある。
顔にも何にもモザイクが掛かってない、無修正だったからって訳でもない。
そうじゃない、おそらく俺たちは全員同じ理由で口が利けなくなっている。
俺は。
もう見たくないのに、それでも画面から目を背けることが出来なかった。
心の中でまさかと叫びつつ、俺はあることを確認する為に最低に醜いその光景から目を逸らせない。
カメラは上からのアングルで粗末なベッドを真ん中に捉えていた。
ベッドの周囲の椅子に腰掛けた数人の『観客』の男たちの脚もフレームに収まっている。
夜の所為か、室内の所為か、さっきの俺のヤツに比べたら画面の色は薄暗い。
薄闇の中、泣き叫んでいるのは粗末なベッドに寝かされた小柄な女の子。
多分せいぜい小学校高学年ぐらいだろう。
長い黒髪の市松人形みたいに可愛い女の子。
その女の子は裸だった。何にも服を着ていない。
肉の薄い真っ白な身体は仰向けにされている。
だが、どう見たって好きでそんな格好をしてるんじゃない。
押さえつけられてるんだ。
圧し掛かる男に。
男は女の子の折れそうに細い脚の間に腰を割り込ませていた。
『…ぃあ、やめてやめ、っと、ぅ、さ』
悲鳴。苦しそうな呼吸。
そこから窺える絶対の苦痛。
悲鳴の隙間を埋めるような荒い呼吸と卑猥な音。
ヤラセじゃないのは多分ここに居る全員が直感で悟ったはずだ。
この悲鳴がニセモノである訳がない。
さっきの俺の未遂とは違う、今度は本物だった。
本物のレイプ映像だった。
泣き叫ぶ女の子がカメラに泣き顔を向ける。
画面越しに俺と彼女の視線がぶつかった。
涙。縋るような眼差し。
一体どれだけの痛みか。
『い…ゃ…たす…たすけ、て…』
がくがくと揺す振られ続ける身体。
カメラに、画面越しの俺に向かって伸ばされる腕。
俺は思わず手を伸ばし、画面の中のその小さな手のひらに自分の手のひらを重ねていた。
けど、ダメだ。
当然だ、届く訳がない、これは今俺の目の前で起こっていることじゃない、俺の手が届かない昔、おそらく数年前の過去だ、俺の手のひらの向こうで悪夢のような映像は垂れ流され続ける。
『…タス…テ…』
画面越しに重なっていた女の子の手のひらがシーツの上にぱたりと落ちる。
その瞬間、咽喉の奥で充満していた熱が弾けた。
「止めろ!消せよ!今直ぐ消せ!」
俺は悪い魔法が解けたみたいに突如怒鳴り声を上げた。けれど、らしくもなく翼が身じろぐ気配はない、画面の中ではまだ惨劇が続いている。
俺は舌打ちすると、半ばその身体を突き飛ばすようにして翼とパソコンの間に身を割り込ませた。
最早声をあげることもできないのか、呼吸困難に陥ってるみたいな切れ切れの苦しげな呼吸音と濡れた粘着質な音、それらに混ざって周囲の男どもの獣みたいな息遣いが時折俺の鼓膜を打つ。
俺は至近距離から聴こえてくるその全部の音に耳を塞ぎたかった。
滅茶苦茶にボタンを押してみる。キーボードの横にあった花束が振動に耐えられず転落したが構ってられない。
押すというより力任せに殴っていたら、唐突にブツッと画面が暗くなった。ヒューンと失速していくモーター音がやけに鮮明に部屋に鳴り響く。
モーターが止まってしまえば、部屋は一気に静寂に包まれる。
俺にはその静けさまでがどうしようもなく不快だった。
別に激しい運動をした訳じゃないのに、俺の呼吸は荒く乱れていた。
「……ふ、ざけんなよ…」
掠れた声が勝手に咽喉から溢れ出た。
拳がぶるぶると震えていた。
「ふざけんなよ!なんでこんなモンがあんだよ!」
振り返ると俺は背後に居た寿樹たちを怒鳴りつけた。でも真っ直ぐに背筋を伸ばして立ってるはずなのに、いきなりぐにゃりと視界が斜めになる。
あれっと思った時には生暖かい体温が頬に張り付いていた。
寿樹だ。いつのまにか俺は寿樹の胸に寄りかかって、肩を抱くようにして身体を支えてもらっていた。
視線の先にはちょうど花束があった。床の上に転がった花束は落下の衝撃で花が曲がって見栄えが悪くなっている。
電車の中で俺はこの花束を落っことしたら悪いことが起きるんじゃないかと思った。
でも違った。
悪いことなんて、とっくに起きていた。
明確な意思なんてなしに惰性で首を動かしてみる。寿樹と目が合う。
「…」
続く言葉を聴きたくなくて、俺は咄嗟に視線を逸らした。勢いよく首を下げたその拍子に猛烈な吐き気が込み上げてくる。
俺は左手で口元を覆うと、右手で寿樹を突き飛ばすようにして部屋を出た。
「!?」
寿樹の声が追いかけてくる。俺はトイレに駆け込むと、便座に手をかけるのと殆ど同時に嘔吐した。
咳き込む背中をすぐに大きな手のひらがさすり始める。
「、大丈夫?」
あらかた吐き出すと、俺は唇を手の甲で拭いながら背後の寿樹を振り返った。
「なあ、今の」
寿樹のその顔を見たら俺はせっかく思いついた自分を誤魔化す為の都合のいい台詞を飲み込まない訳にはいかなかった。
やっぱり。
こいつも思ったに違いない。
再び強烈な吐き気に襲われて俺は便器に顔を突っ込んだ。
「翼、タオルくれ!」
今度は黒川の声。別にそんなに気を使ってくれなくていい、そう思ったところでもう一度嘔吐。さらにもっかい吐いたら朝飯じゃなくて苦い胃液が出てきた。中三になってからは殴り合いで胃液を逆流させるような強烈なパンチを喰らうことはなかったし、ちょっとやそっとの練習じゃゲロったりしねえだけの体力を身につけてたから胃液の味なんか久しぶりだった。
漸く吐き気が治まった俺は便座に凭れながら昨日のことを思い出していた。
昨日、俺がさすっていた小さな背中のことを。
「、タオルだ。吐き気が治まったらそんなところに座ってないで向こうで休め」
寿樹経由でタオルを受け取る。そのタオルを俺は両手で両目に押し付けた。うつむいた俺の周囲を長い髪がまるで檻のように取り囲む。
今と違って、まるで今の俺みたいに髪が長かった。
歳だって違う。
でもその面影は紛れもなく残ってた。
綺麗な黒目がちの瞳。
声なんか今と殆ど変わらない。
「、あっちに行こう」
寿樹が俺の頭を撫でる。立ち上がる気分になれなくて、俺は意味もなくゆるゆると首を振った。ともう一度名を呼ばれたが、俺は嫌々をするように首を振り続ける。小さな溜息の後、肩に寿樹の手が触れた。
引き寄せられて俺の身体は呆気なく寿樹の胸へと傾いてしまう。されるがままに俺は身を起こされ、そのまま抱き上げられた。
俺はタオルを顔に押し付けたまま滲んだ声を絞り出す。震える咽喉をみっともないと感じる余裕さえなかった。
「何であんなもんがあるんだよ…」
寿樹の返事はなかった。
映像の中の幼い少女。
陵辱されて苦痛に涙していた女の子。
それはどう見ても蓑本安良木にしか見えなかった。
翌朝、いつもはぺちゃんこの鞄に制服を詰めこんだ俺は、いつもより一時間早く家を出た。
ヒナコには寿樹と久々に朝練してから学校に行くって云ったけど、もちろんそんな約束はしていない。
家を出て三分後、学校に行くなら横断歩道を渡って左に行くのが正解なのに、横断歩道を渡らずに右折する。
俺は黙々と歩いた。
家から駅までは歩いて十五分くらいのはずなのに、相当早歩きになっていたのか十分もしないで駅が見えてくる。武蔵森までいくらだっけと思いつつ、券売機に目をやったところで俺は思わず脚を止めた。
本当に昨日約束なんかしていない。
なのに、寿樹が券売機の脇の柱に凭れて立っていた。
寿樹は自分の勘の正しさを誇るでもなく呆れるでもなく、本当にごく自然に俺に向かって歩み寄ってくると、「じゃ、行こうか」と武蔵森までの切符を俺に握らして改札へと踵を翻す。俺は苦いような笑いを浮かべて、その背に続いて改札を潜った。
もろに通勤ラッシュの時間帯だったから、構内は人で溢れていた。俺たちは征輝の彼女はどんなだろうとか、関東選抜のキモイ監督の話とか、学校の近所のコンビニの新作のチーズ饅のこととか、くだらない話題を交互にぽつりぽつりと口にしながら電車に揺られていた。
別の線への連絡駅でもあるせいか、武蔵森では多くの人が降りた。改札を潜った先には例の銅像が今日も変なポーズをとっている。ただし一昨日に比べて今日はやけに鳩が多くて、銅像の半径1.5メートル以内の至るところでくるっぽーくるっぽー云っていた。
鳩の大合唱を横目に通り過ぎ、大通りに出てしまうと最早どっちも口を開くことはなく、俺たちは何となく黙って歩いていた。
多分、五分くらいはずっと口を利かなかったと思う。黙っている間、俺は視線を彷徨わせ、意味もなくビルの看板の文字を読んだりしていた。
「嘘吐きは地獄に堕ちるって話、どう思う?」
信号待ちで立ち止まったところで寿樹が急にそんなことを云い出した。斜め上方の見慣れた顔を仰ぎながら、俺はいびつに笑う。寿樹は赤信号の方を見たままだった。
「何だよ、いきなり」
信号が青に変わった。寿樹は何を思ったか俺の右手を掴んだ。そのまま手を繋いで横断歩道を渡り始める。
「昨日の事」
直球過ぎるその台詞に俺の脚は横断歩道の途中で立ち止まりそうになる。
昨日の帰り道、行きと同じで俺は寿樹と一緒だった。でも喋ったのは別れ際の「じゃあな」って挨拶だけで、俺はずっと俯いて目を合わせないことで話しかけられることを拒んでいた。
あの映像のことは一言だって口にしたくなかったから。
「なあ、あのさ」
「僕らは昨日、蓑本さんのお見舞いに向かった」
咄嗟に俺は全然今話す必要のないことを口にして続く寿樹の言葉を遮ろうとした。けれど、寿樹は俺の逃げを許さず、静かだけど強引な響きで言葉を重ねる。
「その車内で君は痴漢に遭遇する。何かがお尻にあたっているなと思いつつ、どうせ鞄かなんかだろって君は気にも留めない。けれど、身体をずらすとずらした分だけ隙間を埋めてぴったり何かがくっついてくる。真後ろに立つ男の息遣いが段々荒くなってきて、耳元ではあはあ云われ始めて、それで漸く君はお尻にへばりついているのは男の手だと、つまり、自分が痴漢に襲われていることを認識した」
「ずいぶんニブイなぁ、俺」
話の内容があの映像のことじゃなかったことに安堵した俺は適当な相槌を返す。あの話をするより全然マシだから話に乗ったけど、俺には寿樹が何で急にそんな変な話を持ち出したのか解せなかった。
落ち着きなくあちこちに視線を向けていると、青信号にとまっている鳩がふと目に付く。何だかそんなところに鳩が居るのは変な気がした。
「やっと自分が痴漢にあってることに気が付いた君はてめえふざけんなと振り返って怒鳴りつけようとした。しかし、君が振り返って口を開こうとした瞬間、君の背後に立っていた痴漢と思しき男はいきなり横に吹っ飛んだ。驚く君の眼前には笑顔で無礼者を殴り飛ばした僕の姿があった」
「…笑顔で、って辺り、お前自分を良く知ってるな」
俺は寿樹に手を引かれたまま、信号機の上の鳩をじっと見ていた。ばさりと鳩が羽を広げる。俺はどうしてさっき変だと思ったのか解った。
こんな所にこいつがひとりで居るのが変なんだ。
あっちの駅の方では気持ち悪いぐらい大量の鳩が身を寄せ合って群れを成していたのに、なんでこいつだけがこんなところでひとりで居るんだよ?
それが何だか酷く腹立たしくて、俺の胸に理不尽な苛立ちが滲む。
「車内に悲鳴が上がる。僕らの周囲から乗客が蜘蛛の子を散らすように離れていく。殴られて倒れ込んだままの痴漢に僕は容赦しない。それはもう、さながら地獄絵図、君の方が狼狽して笑顔で痴漢を蹴り続ける僕をどうにか止めようとするぐらいにね。君はとにかく次の停車駅で僕を引き摺り下ろすと、すいませんすいませんと謝りながら自分と僕の分の切符を投げ捨て、向かい側の線路に飛び降りて柵を乗り越え僕を連れて逃げ出した。猛ダッシュで駅から離れると適当な公園で一休み。そこで僕の手や靴についた血を洗い流したり、が僕にお説教したり。自分たちの身体的特徴を熟知している僕たちは流石に電車に乗れなくて、帰りは10キロ近く徒歩で家路に。今日、こんな早朝からお見舞いにやってきたのは、昨日の今日で午後のあの時間には乗りずらいから、サラリーマンの通勤ラッシュに紛れるため。そう云いながら君は僕を心底忌々しそうに睨む」
俺は漸く寿樹の意図を理解した。
また鳩が羽を広げる。今度は羽が一枚抜け落ちた。ほぼ垂直に落下していく羽根を目で追いながら、俺は寿樹の言葉に返事を返す。
「それを見てきっとラギは笑うな。痴漢の人も運が悪いわね、って」
「うん。だってそれくらい当然でしょって僕も笑う」
横断歩道を渡りきる。信号機の真下を通り過ぎ、しばらくしたところで背後で鳩の羽ばたく音がした。駅に向かったのか解らない、またどっかに自分勝手に飛んでいったのかもしれない、それでも俺は嬉しいような気分になった。だから笑ってみる。
「全然当然じゃねえよ、って俺は余計に怒る」
笑ったつもりなのに、顔が引き攣っているだけな気がした。こんなんじゃ駄目だ。
笑わなきゃ。
全然何事もなかったように笑わなきゃ駄目だ。
「俺たちは昨日痴漢をぶん殴って逃走していた。だから俺たちはあのバカ野郎からカツアゲなんかしてないし翼の家にも行ってない…俺たちは何も見ていない」
昨日。
帰り際、紙袋に入れたディスクを俺に渡しながら翼が云った台詞。
『俺たちは口外しない』
うん、って俺は頷いた。ありがとな、って。
多分、それが一番いいんだ。
他にどうしたらいいのか解らないから。
征輝も、六助も、翼も、そして俺も寿樹も、一昨日のあの時、安良木の心の水面下で何が起こっていたのかきっと正しく理解した。
引き鉄を引いたのはきっと暗闇、そして周囲を取り囲む人。
頭上を横切っていった映写機の光の存在。
無神経で優しさの欠片もない男の硬い腕。
震えて、涙を零して、最後には血を吐くほどの恐怖。
口元を押さえていたのは本当に叫びだしたいのを我慢していたに違いない。
俺たちは何が安良木をあれほどまでに苛んでいるのかを理解した。
けど、理解したからってどうにかできる訳じゃない。
俺たちは事実を知ってしまっただけに過ぎない。そして、事実を理解したからといって、それは決してどれほど安良木が苦しんでいるかを理解できたという意味にはならない。
俺たちは原因を頭で認知しただけで、今でも安良木の心を焼き続けている苦痛を体験したわけではないのだから。
解った振りをするのは簡単だ。可哀想ねと囁いて辛かったねと泣いて見せればいい。でも、それで気が済むのは俺たちの方だ。こんなに心を痛めましたって表明して気が晴れるのは俺たちの方であって、安良木ではない。
血を吐くほどに傷付いている安良木を誰が慰められる?
少なくとも俺は何年間も苦しめられるような記憶を持たない。何年経っても逃れられない苦痛を知らない。そんな俺の口から漏れる言葉はどうせ在り来たりで陳腐で使い古された無意味なものだろう。
だったら何も云わない方がいい。
解ったような顔して憐れまれることを安良木が望んでいるとは到底思えない。
俺の知ってる蓑本安良木は強い女の子だから。
凛として顎をあげて前を見据えてるような女の子だから。
だから、俺たちは何も知らない振りをするべきだ。
何も出来ないくせにしゃしゃり出ることで余計に傷口を広げることもある。
俺は自分が本当は男だったことを知られたくない。こんな姿になっても腹が減ればメシを喰らうし、くだらないテレビでげらげら笑える俺を知られたくない。今では制服のスカートにも慣れてしまったことを知られたくない。こんなになっても生きていられる俺を知られたくない。
同列の次元で語るようなことじゃないかもしれないけど、多分根っこは同じだ。
他人がずかずか踏み込むべきじゃない領域だということは、同じだ。
「俺たちは何も知らない…」
でも、本当は犯人をぶっ殺してやりたい。
あの場に居たクソ野郎どもを全身全霊を懸けてでも全員見つけ出して引き裂いてやりたい。
どうしてあんなものがこの世にあるのか解らない。
どうして安良木があんな酷い目に遭ったのか解らない。
たった二日の間に疑問ばかりが増殖し続けている。
それでも無力な俺たちには何もかもに口を噤むことしかできない。
無力な自分が悔しかった。
例えそれが俺たちが安良木の為に出来る最良の選択だったとしても、知らない振りをするしかない自分が惨めだった。
「僕が殆ど喋るからは黙ってていいよ。蓑本さんが鋭いのはのが良く知ってるでしょ?だから無理して笑おうとせず、とにかくは怒った顔して不機嫌そうにしてるんだ。いつも通りに笑えないなら、下手に取り繕おうとしたって絶対見抜かれる。大筋は今話した通り、蓑本さんのところに居る間だけでいいから自己暗示でも何でも記憶を摩り替えてそう思い込んで」
寿樹の手のひらに力が篭る。
俺もその手を握り返す。
いちいち口に出さなくても今の話だけで十分だった。
繋いだ手のひらを指きりの代わりに、俺たちは無言のままにある約束を交わした。
今この瞬間から昨日という日はフォーカスの合ってない写真のように二重に存在し始める。俺たちは捏造された偽の記憶の中で何も知らずに何も変えずに振舞う。無知を装い安良木を騙す。一生ずっと嘘を吐く。きっと俺たちの間ですら『本当の昨日』について語る日は訪れない。俺たちは生涯ひとつの秘密を胸に沈めて朽ちていく。
俺と寿樹が何年ぶりかに交わした約束は、幼少時代の甘酸っぱさなど微塵もなく、ただひたすら苦いものだった。
ただしお互いがお互いを絶対裏切らない、そう信じる思いには傷ひとつ付いてない。これまでの長い付き合いで些細な約束は破ったことはある。でも、俺と寿樹は何だかんだ云って真剣に結んだ約束は一回も破ったことはない。だから誰に罵られようと、俺たちは一生嘘を吐き続けることだろう。
もし嘘吐きが地獄行きだというなら、それでいい。
それでも俺は永遠に嘘吐きであり続けることを選ぶ。
息を吸い込むと、俺はことさら軽い調子で口を開いた。
「見舞いの花、そういや買ってないな。手ぶらだぞ、俺ら」
「花なんか持ってたらせっかく時間ずらしたのに目立つし、それに僕たちはそれほど蓑本さんのこと真剣に心配してるわけじゃないし、今日はお見舞いと称したサボリだから、まあいいんじゃない?」
「そうだな、今度ヒナコにクッキーでも焼いてもらえばそれで十分だよな」
俺は笑う。笑える。
大丈夫だ。
俺はさっきの寿樹の言葉を反芻して、頭の中でできるだけ具体的なイメージを思い浮かべてみる。
試合の前と同じだ、メンタル・コントロールぐらい何時だってしてきた、試合の前から勝てないなんて思ったら良いプレーなんてできっこない、余計なことは考えない、集中しろ、大丈夫だ。
車道のクラクション、通り過ぎる人々のお喋り、店先の宣伝テープの声、騒音にまみれながら俺は神経を研いで記憶を塗りつぶしていく。
そんな中、俺の頭上、雑音に飲まれて聞き逃しそうな小さな声。
「きっと天国より地獄のが面白いよ」
その言葉の後、もっと小さな囁き、それも俺の耳には届いていた。
『一緒に地獄に堕ちよう』
俺は返事の代わりに寿樹の手を握り返した。
「あれ?」
一昨日来たばかりのマンション、そのエントランスホールで自動ドア越しに蔦の絡んだアーチやその向こうの道路をぼんやりと眺めていた俺は、明らかに怪訝な響きを帯びている寿樹のその声に振り返った。
例の液晶画面が嵌った楕円形のオブジェの前、寿樹が顎に手を当て僅かに首を傾げている。
「どうしたんだよ?」
俺は寿樹に近付いて、横からオブジェを覗き込む。液晶画面には顎に手をやった寿樹と横っちょから覗き込んでる俺が映っていた。よく見ると、液晶の上のところに直径1センチ程のカメラのレンズが埋まっている。でも、そのカメラの存在に気が付いたぐらいで、俺には寿樹の訝しげな態度の理由が解らなかった。
「何だよ?これがどうかしたのか?」
「反応がないんだよね。そっちにあるボタンが各部屋直通のチャイムで、それを押せばその部屋の住人がそれぞれインターフォンで対応するはずなんだけど」
「じゃあ押してみればいいじゃねえか。ラギの部屋何番だっけ?」
「809号室。だから何にも反応がないんだよ、押しても」
「え?」
俺はいっぱい並んでいるボタンの中から809を速攻で見つけ出すと人差し指ですかさず押してみた。
確かに寿樹の云う通りだった。めいっぱい下まで押し込んでみたってかちかち云うばっかで画面に何ら変化はない。
俺の胸に急激に嫌な予感が広がっていく。
「寿樹…」
「待って。ここに御使用にあたってがあるからちゃんと読んでみるから」
俺は画面に映りこまないように一歩下がった。カメラに撮られることが何か嫌だった。
説明書きに視線を走らせている寿樹の背中を俺は不安な面持ちで見つめていた。どうか先に何か別のボタンを押さなきゃならないとか、ただの操作ミスであって欲しい。あるいは単なる故障であればいい。
俺は奥歯を噛み締めてそうであるよう、祈っていた。
その俺の背後から自動ドアの緩い電子音、何を期待していたのか、それとも何かに怯えていたのか、俺は物凄い勢いで振り返る。
「……い…っしょと」
落ち葉の詰まった透明ビニルと箒を手にした、くすんだブルーの作業着を着たおじいさんが入ってくる。
管理人室とプレートの掲げられた入ってすぐ右の方の病院の受付みたいな窓、その横のドアへと三歩ほど足を進めてから、おじいさんが漸く俺たちの存在に気が付く。
こんな朝っぱらから私服のガキどもが訪ねてくるなんて不審に思われて当然だ、だから咄嗟に云い訳を用意しなければと思ったのに、おじいさんは意外にも眉を顰めるどころかにっこりと人の良さそうな笑顔を浮かべたのだった。
「おはようございます」
「あっ、オハヨウ、ゴザイ、マス」
おまけに挨拶までされて、面食らいつつ俺は軽く頭を下げる。俺の背後から寿樹もおはようございますと挨拶を返す。
「失礼ですが管理人の方ですか?こちら、ボタンを押しても反応がないのですが、故障しているんでしょうか?」
「いいえ、故障はしてませんよ。809号室のお嬢さんのお友達の方ですよね?」
「えっ?何で知ってんだよ?」
云い当てられて俺は思わずデカイ声を出してしまう。おじいさんはゴミ袋と箒をとりあえずホールの隅の方に置くと、にこにこと微笑みながらこっちに近寄ってくる。
「一昨日、具合が悪そうなお嬢さんを連れて来なさったでしょ。それも気になったし、そちらのお嬢さんが天女のようにべっぴんさんだったのと、そちらの貴方がでいだらぼっちのように背が大きいからびっくりしてね、よぅく覚えてますよ」
「あの、お、ぼ…えと、ワタシたち、お見舞いに来たんです、でもボタン押しても反応なくて」
「反応がないのは電気が通ってないからですよ。そこのボタンは各部屋のインターフォンの電源が入ってないと、押しても鳴らないようになってますからね。うぅん、急のことだったから連絡が遅れているんですかねぇ、昨日ここを引き払われて出て行ってしまったんですよ、あそこの御一家は」
その言葉に俺は目の前が真っ暗になる思いだった。
嘘だろ、って云いたかった。馬鹿なこと云うなよ、って切って捨てたい。
でも、俺の頭はどこかでするりと納得していた。さっきからずっと嫌な予感がしていたから、俺の予感は滅多に外れることはないから、だから信じたくない反面、ああやっぱりだって最悪の状況を受け入れている。
「昨日突然ですか?普通は引越しってきちんと方々に連絡してからするものですよね?」
そう云いながら寿樹が俺の肩を引き寄せた。おじいさんに向かって喋り終わったところで、小さな声で「、しっかりして」と囁く。
その声にはっとする。
慌てて俺は背筋を伸ばした。
「ああ、うん大丈夫」と半ば条件反射で頷いていたものの、相当やばいぐらいに呆然自失としていたのか、おじいさんは酷く気の毒そうな視線を向けてくる。
「ええ、役所やガス電気水道、いろいろ手続きが必要ですからしたくなったからといっておいそれとできるものではありませんよ。ですから、もともとお引越しなさる予定自体はあったんです。ただし、それは来週のはずだったんですがねぇ、どういう訳か一昨日の夜、事情があってどうしても明日引っ越さなくちゃならなくなった、って。あとたったの八日がどうしても我慢できなかったんだから、よっぽどの事情があるのかもしれないけれど…三年ここの管理人やってますけど、初めてでしたよ、こういうことは」
「あの、部屋見せてもらえませんか?もしかして書置きとか残ってるかもしれないから」
おじいさんは云い辛そうに、皺の寄った目元を何度も瞬かせる。
「一応、出て行かれた後に私が確認したので…残念ですが何も残ってないとは思うけど……それでもいいなら、構いませんよ」
「お願いします」
俺は膝に額がくっつきそうなぐらい頭を下げた。
おじいさんは「ちょっと待っててくださいね、今鍵を取ってきますから」と管理人室の方へとちょこちょこと小走り気味に歩き出す。俺はその背中にもう一度お願いしますと頭を下げた。
「、大丈夫?」
「ああ…」
俺は奥歯を噛んだ。
畜生。
このタイミングは何だよ。
予定を前倒しにしてまで引っ越さなきゃならない理由は何だ?
俺たちにここを知られたからか?
少なくとも俺にはそれしか心当たりがない。
『先生』と呼ばれていたあの人。
安良木を傷つけないと云ったあの人。
なのにあの映像は何だ?
傷つけないって云ったたくせに、全然安良木のこと守ってないじゃねぇか。
あの時一体何してたんだよ?どうして安良木を助けてやんなかったんだよ?
昨日の寿樹の言葉によって一旦は鎮静化した不信感が、俺の胸の内で再び猛スピードで立ち込め始めている。次にあの人を目の前にした時、俺は冷静でいられる自信がない。
戻ってきたおじいさんの後に続いて移動して、俺たちはエレベータに乗り込む。ガラスの箱に収まると、まるで狙ったようなタイミングで俺も寿樹もその壁に背を預けていた。
八階を目指しながら、俺はこれからどうしたら良いか考えを巡らそうとした。けど、俺はどうすべきなのかどうにか安良木を探すべきなのかより、安良木が今どうしているのか無事なのか、そんな考えても仕方ないようなことばかりがどうしても頭を占領してしまう。
「引っ越し先は御存じないですか?」
寿樹のその質問に俺はバネが弾けるように顔を上げる。そうだ、もし解るんならこの後すぐにそこへ行けばいい。
だが、俺の目に映ったのはおじいさんの心底申し訳なさそうな顔だった。
「いやあ、私は雇われ管理人だからちょっとそこまでは…あとで親会社の方に電話で訊いてあげてもいいけど、お嬢さんのお友達なら学校で会えるんじゃないのかい?それとも篠守さんのお嬢さんと学校が違うの?」
俺たちは感電したみたいに寄りかかっていた壁から身を起こした。
「あの、今なんておっしゃいました?」
「学校が」
「そこじゃなくてなんかシノモリさんとか云ってなかったですか?」
俺と寿樹の剣幕におじいさんは訳が解らないとばかりにきょとんと目を丸くする。
「ええ、篠守さん。何かおかしいの?違う読み方でもあるんですか?私はそう呼んで御挨拶してましたけど、一度も訂正されたことはなかったですよ」
「いえ…いんです、気にしないでください……」
俺は酔っ払いみたいな縺れた足取りで再びエレベータのガラスの壁へと凭れかかる。けれど背中がずるずる勝手に横に滑って、直角になってる隅っこに肩がぶち当たることで漸く俺の身体は停止した。
「…蓑本と篠守」
「うん。そうだね」
聴き間違えも書き間違えようもない、という響きを言外に匂わせた寿樹の声。
俯いた俺の視線の先、寿樹の手は硬く拳に握られていた。まるで俺と同じ苛立ちと混乱を表しているようだと思う。
一昨日から数えてもう何十回と胸の中で繰り返した問がある。
答えの返る当てはない、それでも俺は問わずにはいられない。
安良木の身に一体何が起こっているんだ?
清々しい軽快な音に合わせてドアが左右に開く。俺たちはおじいさんを先頭にエレベータを降りた。
鍵を開けてもらって中に入る。
玄関で靴を脱ぐ。居間へと続く直線の廊下を踏む。あのトイレの前を通り過ぎ、突き当りのドアを開ける。
何も無かった。
家具どころか新聞紙一枚ない。
そこに誰かが居たという痕跡は綺麗に拭い去られている。
がらんとした寒々しい居間をさらに突き進み、例の部屋のドアの前に立つ。
開けてみる。
覚悟していた通りだった。
空白。
ここも空っぽだった。
俺は初めてその部屋に脚を踏み入れてみる。
部屋の中心に立って、部屋を見回してみた。多分六畳ぐらいだ。
俺は出来ることなら叫びだしたかった。
一昨日と同じように雨戸が引かれっぱなしになった部屋は薄暗い。
俺は雨戸のない、もうひとつの窓へと近付いた。
もう格子はない、けれどそこには確かにあの格子を留めていた螺子の跡が在った。
俺は指でその穴を撫でてみる。
「ラギ…」
まるで雪が融けるように消えてしまった安良木の痕跡は、よりによってあの忌々しい檻の名残だけだった。
|