|
1998年、11月7日。
『ねーねー行こうよー』
俺は現在、とある駅前にバカみてーなカッコでバカみてーに突っ立っている。
こんな格好は断じて俺の趣味ではないし、したくてしているわけじゃない。のっぴきならない事情があってのことなのだ。
しかし、理由さえあれば『ハイ、ソーデスカ』と容易く納得できるほど人間は単純にできていない。
土曜の所為か近所のイベントの所為か、とにかく人で溢れ返ってる駅前をそんなアホみてーなカッコで立ってることを強いられている俺の機嫌はもちろん最悪。
おまけに当然することなんかないもんだから、パーカーのポケットに手ェ突っ込んだ姿勢で足元のタイルを親の敵みてーに睨みつけている。我ながらまさに完全な八つ当たりだ。その変な渦巻き模様をサーキット代わりに、俺の視線はさっきから無意味にその上をぐるぐる何往復もしている。
『カラオケも食事も全部奢るからさー』
ちなみにバカみてーなカッコっつーのは某アイドルグループの某メンバーが某曲で着ていたような、ケツの見えそうな超ホットパンツに膝まであるだっぷりしたルーズソックスだ。
ホットパンツは流石に女もんだが、上のパーカーは何とか男物。それから頭にロサンゼルス・ドジャースのキャップ。
これは被るなと云われたが、コレだけは譲れんとゴネにゴネまくって何とか了承をむしり取ったものだ。こんな恥ずかしいカッコで、顔隠すもんもなく立ってられっかっての。
『ほんっっと、可愛いねー。俺マジびっくり』
なんでドジャースかってーと、石井一久が好きだからだ。野茂や長谷川やイチローも別に嫌いじゃねーけど、俺は日本人メジャーリーガーじゃ石井が一番好き。
だって人間のくせして素手で150キロの球投げんだぜ?スゲーよなー。あんな球をデットボールで喰らったりしたら俺は泣くね、恥も外聞もなく。まぁ、石井よりランディ・ジョンソンのが速いけどさ、100マイルだもん、シャレんなんねーよ。
『さっきからここ居るよねー』
でもほら、俺、日本人だし?こんな時だけナショナリズムってワケじゃないけど、やっぱ石井のが好き。
あのノーコンなのに球威が凄いから打てねえってのもさー、俺は好きなんだよなー。なんかいいじゃん、テクニックが悪いなんて思ってないけど、スピードに関しちゃほんとにガチンコ勝負っぽいだろ。それで勝つ、ってやっぱカッコいいじゃんか。
『待ち合わせ、すっぽかされちゃったんじゃないかなー』
『ね、行こう、あ、じゃ、それがダメなら携帯の番号教えてくんない?』
まぁ、あんましメジャーに選手が流失しちゃうとその分日本球界は面白くなくなるけど。
まぁ、俺そんなスゲー野球ファンってワケでもないし。
『俺の番号はねー』
『ね、ほんと時間ない?行こうよ、絶対楽しいから』
『君みたいな子とこの先絶対出会えないからさ、マジ俺君と話したい』
サッカーでも大分日本人が認められてきて、中田や……
『頼む、ねぇ、話聴いてよ』
肩を掴まれた。
駄目だ。
もう、我慢できねぇ。
俺は無理矢理思考を逸らすことを諦めた。
無理。ホントもう無理。ハーイ、ボク、あと5秒でキレまーす。
「あ、やっと顔上げてくれたー」
顔を上げた先にはキモチワリい笑顔浮かべてるクソ野郎どもが5人。
俺の唇に自分でも得体の知れない笑みが浮かぶ。
目の前のアホどももつられたようにだらしなく笑う。
アハハ、この、バーカ。
逝き先も知らずに笑ってんじゃねぇよ。
てめえら全員、今から地獄に送ってやる。
俺が生温い笑顔を浮かべたままパーカの中で拳を握った時だった。
「〜お待たせ〜」
俺がブチキレるのを見計らったかのようなタイミングで(って、実際見計らっていたわけだが)、状況を弁えない呑気な声が頭上から降ってきた。
俺を取り囲んでいるナンパヤローどもより頭ひとつ分以上デカイ長身。
邪魔が入ったことに俺はちっと舌打ちする。
珍しく止めに入ってきやがったのはこんな所で喧嘩すんなって意味か?確かに今日はこの後約束もあるし、俺と寿樹の他にもうひとり連れが居るのだから、こんな駅前でファイトクラブをしている場合ではない。
馬鹿どもが寿樹のデカさに呆気に取られている間に、俺は肩をねじ込むようにして包囲網を突破した。
「身の程知らずに声をかけちゃう気持ちも解るけど、この子は僕のだから頑張って他所を当たって下さいね〜」
朗らかに相手を馬鹿にしくさった台詞をわざわざ吐きながら寿樹が俺の後を付いてくる。何が僕の物だ、と本来なら殺人ボディーブローもんだが今回は見逃してやる。
ほんのついさっきまであの馬鹿どもをボコろうとしていた分際で云うのもなんだが、そろそろ本当に約束の時間が迫ってきているのだ。
「ラギ!」
変なポージングの銅像の後ろから両手で口元を覆った安良木がひょこっと現れる。
「もう気ィすんだだろ!はやく行こうぜ!」
俺の刺々しい口調に安良木の瞳が余計に三日月を描く。ふふ、と聴いてるこっちがどきっとするような声が細い指の下から零れ、けれど結局堪えきれずに声を上げて安良木は笑った。
「ああ、おもしろかった……駄目じゃない、、10分って云ったのに、まだ6分しか経ってないわ」
「冗談じゃねえ!」
安良木が目尻の涙を拭いながら、それでもまだくすくすと胸を震わせている。俺はキャップのつばをぐるりと後頭部に回しながら、安良木を睨んだ。
「大体コレ着て来いってだけの話だったはずだろ?こんなん予定になかったじゃねーか、やってられっかっつーの」
「あら…私の云うことなんでもきいてくれるんじゃなかったの?」
俺はぐっと言葉に詰まる。
「云ったけど………云ったけど、でも、何個もなんて云ってないぞ」
俺は男らしくないセコイ反論を試みる。
つまりぜーんぶ罰ゲームなんだよ。
俺がモー娘。のゴマキ(あ、云っちゃった)のコスプレもどきをさせられてんのも、10分間に何人ナンパしてくるか実験させられたりしてたのも、全部ついこの間のアレに対する罰ゲームなんだ。安良木の声を無視して暴走した俺のせめてもの謝罪なんだ。
でも、それにしたって、俺は「何でも」って云ってんのに安良木のお願いは俺には何が楽しいのかさっぱり解らんものばっかだ。こんなアホみてーな衣装をわざわざ買ってきて俺に着せたりすることの何がそんなにオモシロイんだ?
寿樹と安良木はすーげぇ楽しそうだけど。
…そうなんだよな。なんだかんだ云ってこの二人は気が合うみてーなんだよな、特に俺苛めに関して。
俺に何を着せるか話し合っていた二人はとてもイキイキしてやがりました。アンミラとモー娘。とミニスカポリスで真剣に議論を交わせるこの人たちを本当に冗談抜きで心底どうにかして欲しい。
そのときの光景を思い出して思わず俺がうんざりしていると、安良木は唐突に笑みを消した。
涙で濡れた目で俺を一瞬だけ見つめ、そしてすまなそうに眉根を寄せると俺から視線を逸らせて俯いてしまう。
「そうね…ごめんなさい、調子に乗ったりして……」
「え、あ、う、いや、いいよ、俺が何でも云えっていったんだし!」
見えもしないのに、俺は自分の頬がかーっと紅くなって行くのが解った。
お、俺が悪いんじゃなくて、今のは安良木が悪いぞ!
なんか……なんかすっげえ色っぽかった!
どもる俺の視線の先で安良木の睫毛が震える。
「あ、ちょ、ラギ」
泣くのか!?って俺が慌ててその顔を覗き込もうとするより先に、安良木が俺の胸にしがみついて来た。
咄嗟に俺は天に向かって両手をホールドアップさせる。
情けないが俺のほっぺはホントに林檎のようになっていることだろう、畜生。
「ラギごめん泣くなよ!俺もう文句云ったりしないからさ、なく」
「っぷ…アハハ!」
がばっと安良木が顔を上げる。
……ちっとも泣いてなんかいねぇよ、珍しく大口開けて爆笑してやがる。
「ラァ〜ギィ〜?」
呪うような低音を吐き出す俺からするりと離れ、くすくす笑いながらウドの大木を盾にして安良木が小首を傾げてにこりと微笑む。
「ごめんね、。私最近、好きな子ほど苛めたくなるの、病気かしら?」
なんだよもう!
可愛いんだよ、畜生!
俺はやり場のない怒りをぶつけた。
「痛いなぁ〜どうして僕を蹴るのさ〜」
「ウルセー!ラギを蹴れるわけねぇだろ!」
俺が男らしく云い切ると、寿樹はふうと深刻そうに溜息を吐いて脇の安良木に視線を落とす。この二人が並ぶと身長差が40センチ以上あるから、遠近法が狂った絵みたいで変な感じだ。
「いいな〜蓑本さんはに抱きついても怒られなくて〜。僕はすぐ暴力をふるわれるんだよね、どうしてなんだろ〜。好きな相手がサドの場合、僕が努力してマゾになるべきなのかなぁ?」
「須釜君は真性サディストだから無理だと思う」
「俺はサドじゃねェ!お前がキライなだけだ!」
「あら…」
安良木の瞳がきらりと光る。
「は意外と自惚れ屋さんなのね。須釜君は好きな相手、と云っただけよ、って云った訳じゃないのに自分のことだって自信があるのね?」
「ちっちがっ…」
云い淀む俺からわざと視線を背けて、寿樹がふっと哀しげに目を伏せる。
普段へらへらボケボケと嘘なんて吐きません〜って顔してるくせして、実は寿樹は演技派だ。天然な振りして意外と計算高いから、コイツだけは本当に信用ならねぇ。
今だって10人が見たら10人全員が嘘偽りのない本心だと勘違いをしそうな、こんなアホな話題に甚だ不似合いな苦い自嘲を浮かべてみせる。
「いいんです蓑本さん、は僕の心を知ってて弄んでいるんですから。Tシャツだけしか着てない姿で僕を誘惑したくせに胸をちょっと触らせて終わり、人をその気にさせといて押し倒してみればキスもさせてくれない、ハニーちゃんは男心を弄ぶ可愛い小悪魔なんですよ」
「てゆーかそれ全部被害者は俺の方だろが!」
悪魔はテメーの方だ、このエロじじいめ!
って、俺も突っ込んでる場合じゃないよ、時間がねぇんだよ、こんなことしてる場合じゃないだろが!
「おい、ほんとに行かないと…」
安良木が空中でひょうたんを描くように手を移動させる。
「うふふ、の身体はね〜、胸がふかふかしてて気持ちいいの。でも背中や腰周りには無駄なお肉がなくって、きゅって締まってて」
「そうなんだよね〜無駄な肉はないのに絶対Cカップはあるよね〜、僕的にはもうちょっとあってもいいぐらいなんだけど〜」
「ちょっと待てーい!」
なんで俺は安良木にまでセクハラされてるんだ!
ああもう、つきあってらんねぇよ!
俺は馬鹿なポーズを取ってる銅像の下に二人を置き去りにしてひとりで勝手に歩き出す。
そうだよ、さっきっから一歩も移動してねぇんだよ。遅刻だぜ、きっと!
「あ、待ってよ。どうして先に行っちゃうのよ」
安良木が追い付いて来て、俺の左手に指を絡める。俺はまたどきどきして、つい歩みを緩めてしまう。
「そうだよ、酷いなぁ、自分から誘っておいて」
寿樹が俺の右手を握ろうとしたが、それは容赦なく振り払う。誰がヤローと手なんか繋ぐかよ、キモチワリイ。
俺は安良木の手を引いて少しスピードを速めた。
「、そんなに急ぐことないじゃない。知らない土地で焦っても良いことないわよ?」
「だって遅刻しちゃうだろ、お前らの所為で!」
俺は二人を交互に睨んだ。
「翼、待たせたりしたら絶対怒るぜ、ヤダよ、俺、あいつにぐちぐち云われんの」
「あら、平気よ」
俺はえ?っと思って目をぱちぱちさせた。
なんかあんのか、翼を怒らせない方法が。
安良木がにっこりと微笑む。
「だって怒られるのは私じゃなくてだもん」
……………。
……………………そうですネ、この面子だと椎名さんに小言を喰らうのは確実に俺だけですネ。
「……オネガイデス、イソイデクダサイ」
うなだれてそう告げると、安良木は囀るように小さく笑い、俺の指をするりとほどいて数歩駆け出す。
こっそりと溜息を吐く俺の頭を寿樹がぽんぽんと撫でた。
云わないけど、こいつも気が付いているのだろう。
安良木の様子がおかしいことに。
あの事件から二週間後、俺の手の包帯が取れた頃と前後して変なんだよ。急にテンション高くなって笑ったかと思ったら、その次の瞬間には憂鬱そうな無表情になってたり。
今だってそうだ。
安良木は普段冗談でべたべたしたりしない。抱きついてきたりはするけど、それは服という遮蔽物があるからだ。直接肌と肌が触れ合うことに対しては厭う節さえ在ったのに、自分から手なんか繋いできて。
俺は別に嫌じゃないよ。
でもただ心配なだけだ。
俺だって安良木に自分が男だったのに、どっかの寂しがり屋のアホに自然の摂理を捻じ曲げられて女にされたことを話していない。
同じように安良木にだって俺に云えないことがあるんだって思う。
だから別に何にも云ってくれなくてもいい。
本人がまだ一人で頑張れるっていうのなら、俺は黙ってる。
まぁ、こうゆうふうに考えるのは俺自身が意地っ張りな上、人に指図されたり干渉されたりすんのが大っ嫌いなタチが影響してんだろうけど。
横に並ぶ、45度上の顔を仰ぐ。
寿樹は笑ってる。
俺はこいつの、こういう何でも解ったような顔が大っ嫌いだ。
だからその手を引っ掴むと、先を行く安良木を追い駆けて走り出した。
「うおーすっげ…」
どうにか遅刻を免れた俺は翼のマシンガンの餌食にならずに済んだ。だって俺たちもほんとは遅刻してたんだけど、それよりさらに翼たちが遅刻してきたんだもん。
理由を尋ねると、翼たちの地元での待ち合わせに直樹が寝坊してきたらしい。俺は翼の尻馬に乗って直樹をなじりながら、心の底でそのサルっぷりに感謝した。尊い犠牲をありがとう、サル。
で。
俺たちご一行がどこに来たかっていうと
「武蔵森は幼稚舎から大学院まで抱えたマンモス学園だからな。俺たち公立のとことは金のかけ方が違うよ」
「はぁ〜…」
俺はほとんど呆れかえってその豪奢な校舎を見上げていた。
俺、今まで自分の通ってた小学校や中学を特に汚ねえ校舎だなーとか思ったことなくて、アレが普通だと思ってたんだけど、なんかこうまで違いを見せつけられるとなぁ……。
壁とかちゃんと白いんだぜ?黄色っぽい白じゃなく、ほんと真っ白。ひび割れとかしてなくって、ペンキの剥がれてるとこなんか見当たらない。
くそう。
建物の造詣依然にもうその時点で勝負にならん。
校舎の影に在るらしいグラウンドの方からぽんぽんぽんと花火が上がる。俺はそれに紛れてちょっとだけ溜息を吐いた。
ま、そんな勝負しに来たわけじゃねぇし。
気を取り直そう。
昨日から武蔵森は学園祭をやっている。この前また飛葉中に遊びに行ったら翼が教えてくれた。東京選抜には渋沢とか藤代とか武蔵森サッカー部の顔がいるからソースはそこだろう。俺が行きたいって云って、んじゃ、行ってみるかって話になったんだ。
パーカのポケットに手を突っ込んだまま、俺は翼を振り返った。
「んじゃ、行くか?」
「ああ」
ちなみに翼は今日は女連れ。
飛葉中サッカー部のマネージャーもやってる子。俺も何度か会ったことがあるけど、最初に見たときはびっくりしたぐらい翼並に綺麗な顔した子。二人して立ってるとすげーぞ、何かオーラ出てるもん。
ただし、さすが翼が選んだだけあって、翼同様外見を裏切った破壊力も抜群だ。
さっきも寿樹を見るなり可愛らしいひとさし指を突きつけて、『あ、わかった。翼、この人でしょ?キョウチョウセーやジセイシンための栄養が全部身長に回ってんじゃないのってぐらい、無駄に背が高くて、翼が最近一番ムカついたってゆう人〜』ってそれはそれは愛らしい笑顔で云い切ったのだ。
場が凍ったね、一瞬。
どないすれっちゅーねん!
って、思わず脳内でエセ関西弁でツッコミを入れてしまったほどだ。
寿樹は『うん、そうで〜す、僕が近年稀に見るほど椎名君をご立腹させた、背の足りない可哀想な人に分けてあげたいほど無駄に背が高い人で〜す』とかにこにこしながら彼女に返してたけど、お前それケンカ売ってんじゃん!と内心誰しも思ったに違いない。さりげなくあからさまな毒を吐くんだから、相変わらず恐ろしい神経だ。
でも寿樹も恐いが、この寿樹の返答にニヤリと笑い返した翼も恐い。絶対、後でなんかする気だ。恐い、恐すぎる。
俺は暴君と悪魔の魔界大戦が勃発したら、安良木を連れて速攻で遁走することをすでに決心している。
「おい、、先に云っておくけど面倒だから迷子になるなよ」
「バッ、なるわけねぇだろ!」
「解らんで〜、お前ならなるんちゃう?」
「「お前が一番怪しいんだよ、サル」」
俺と椎名の突っ込みにみんなが笑う。
それを合図にしたようにぞろぞろ赤白青の三色をあしらったアーチを潜った。
入り口でパンフを貰って、どこに最初に行くとも決めてなかった俺たちは人込みの流れに乗ってぞろぞろと移動していく。
今日集まったメンバーは俺たち3人と、柾輝を抜かした飛葉中サッカー部プラスマネージャー。柾輝は、って翼に訊いたら何か意味ありげに『あいつもいろいろ多忙な身なんだよ』ってにやにやと笑った。よく解らん。
この大所帯じゃ横一列に移動できるわけもなく(でもなんかそういうテレビ番組あったよな、横一列でぞろぞろ歩くの。俺、懐かしのナントカで見たことあるぞ)、先頭に翼と彼女、そして安良木、一番後ろに畑兄弟と寿樹、んで直樹と俺がど真ん中二列目って編隊が組まれた。
ディフェンダー同士の寿樹たちがサニョルとかリザラズとかの話すんのは解るけど、翼と安良木がVAIOのニューモデルがどうのエリクソンとの携帯がどうの意気投合してるのは何なんだ?
また安良木の意外な一面を見てしまった…。
「…お。あった、キックターゲット武蔵森。なんだ、午後じゃん、2時からだってよ」
「お前、ほんまに出るんか?」
「あったりめーだろ、何の為にここまで来たと思ってんだよ、渋沢と勝負するために決まってんだろ」
そうなのだ。
なんでこんな縁もゆかりもねーような学校の祭りに俺が来たがったかって云うと、この清々しく某番組をパクってるサッカー部主催のアトラクションが目的だったのだ。
「勝負って、確か渋沢の旦那はパーフェクト出した時のアルティメット・チャレンジなんやろ?お前パーフェクト狙えるほどコントロールに自信あるんか?」
「ない。絶対無理」
直樹がベタにずっこける。
大変だなぁ、大阪人は。
「アホか!お前、云うとること矛盾しとるで、パーフェクト出せへんのに旦那と勝負できるわけないやろ!」
「俺はどうしても渋沢とヤリてーんだよ」
もう普通に試合で勝負するって道はどこぞのバカの違法投機によって塞がれちまったからな、こういうチャンスを逃さねぇ手はないだろ?
直樹が今度は気持ち悪く身をくねらせる。
「うっわ…ヤリたいってエッチな女やなー。女から慎みを取ったら姦しさしか残らへんで」
俺はわざとらしく両手で頬を覆ってるサル井上を横目で冷たく睨んだ。
「サル。ひとつ良いことを教えてやろう。例えお前がどんなにサルに近い哺乳類だとしても、一応人間なんだから普通は女にそういうことを云うとセクハラで訴えられちゃうんだぞ」
「チッ、住み難い町やなホンマ東京っちゅうとこは!これだから都会は好かん!」
「いや、ソレ東京関係ないし」
「お前さん、どないするっちゅーねん、色仕掛けでもするつもりか?」
「だからいい加減そっちから離れろよ、エロザル!椎名に頼べばいいんだろが!」
直樹がぽんと手を打つ。
「ああ……なるほど、翼に色仕掛けしてもらって旦那を篭絡してもらうんか」
「そうそう、翼にね〜ってアホか!翼に渋沢紹介してもらうんだよ、普通に!ごく普通に、オトモダチとして!そんで頼み込んでなんとか勝負してもらうんだよ!」
「いやあ、ノリツッコミをしてくるとはお前もなかなか侮れんのう。いい筋しとるで」
「……実は俺、黙ってたけど、関西人養成ギブスを家じゃ使ってるんだ」
「何ィ!?あの幻の!?」
「そう。親父が関西人になれなかった夢を俺に託して、幼い頃から強引に飯喰う時も風呂の時も寝る時さえも着用を義務付けられてたんだ…っ」
「……苦労してきたんやなぁ…もうええ、みなまで云うな、俺の胸で好きなだけ泣け、ただし今日だけや、明日からはまた厳しくいくで!」
「サル…っ、顔は不細工だけど良い奴だよな、お前って奴は!」
「わはは、不細工だけど心は錦や…ってお前それ貶してるやん!」
直樹が俺にツッコミを入れる。
手の甲で肩をバシッとやるヤツ。
おお、本場のだよ!って俺がうきうきと調子に乗ってさらに口を開こうとしたら、心底軽蔑したような顔した翼がこっちを見ていることに漸く気が付いた。
天使のように愛らしい顔に侮蔑の色を滲ませて翼が冷淡に微笑む。
「お前らって本当に類友だよ。馬鹿で煩いところがそっくり。みっともないからそれ以上僕に近寄るなよ、知り合いだと思われたくないからさ」
ガーン!
ヒデエ!嫌過ぎる!
云い返そうとしたら、その前に翼たちは人の流れに任せてさっさと体育館の中に入ってしまう。
俺は後に続くのを瞬間躊躇って巨大な体育館を見上げた。
オイオイ、流れに任せてここまで来ちゃったけど、体育館入って何すんだよ?
まあ、今日は全員一日中暇だって云ってたし、別に適当にぶらぶらしてたって誰も困んねーけどさぁ。
後ろの寿樹たちをちらりと振り返ってみたが、別段異論がある様子もない。うん、…まあ、いっか。
中で何をしてるのか知らないまま、俺もとりあえず後に続いて体育館に足を踏み入れてみる。
……うーわー。何なんだ、もう、この学校は。
まーたデカイ体育館だね、普通中学の体育館なんかバスケのオールコート一面の中にハーフコートがふたつだろ?なのにここ、オールコートふたつ分あるんですけど。しかも超キレイでやんの。
畜生、参上とか落書きしたろか?
俺たちがくぐってきたのは一番後ろの入り口だったんだけど、6個ある扉の内、他のはすでに閉まってる。
俺たちの居るあたり、オールコート一枚分相当の後方にはずいぶんな人数が溜まっていて、何重にも重なって分厚い人垣を作っている。さっき人垣の隙間からちらりと見えたんだけど、残った前方の面積には椅子が置かれているようだった。でも隙間なくずらりと並ぶ人間の後頭部から察するに、多分とっくにそっちは満席状態だ。
俺は顎を上げて、さらに人垣の奥に何があるのかを見極めようとした。
一段高いところに長方形の白いもの。
ああ、なーんだ。
壇上にスクリーンが下ろされていて、そんでもって体育館でこの人数ってことは映画でもやんだな?
俺は周囲をさらに見回してみる。
あ、二階席もあるんだ…もう満杯みたいだけど。その座席の後ろにある窓は全部暗幕が引かれてる。やっぱ映画だな、こりゃ。
きょろきょろしてると、翼から離れて安良木がくすくす笑いながら俺の所にやって来た。
そしてにっこり可愛く笑いながらひとこと。
「類友」
だから、それ嫌過ぎるって!
「勘弁してよ…」
うなだれる俺に安良木は微笑みながら首を傾げてみせる。
「ここで何をやるのかしら?何となく人波に任せて入っちゃったんだけど」
ああ、そっか。
安良木は背ぇ、ちっちゃいからな。こっからじゃスクリーンも見えてねーのか。そういや、前に目もあんまし良くないって云ってたよなぁ。
どうしよ、見えねーんじゃつまんないよな。
「多分だけど、えい」
がしゃーん、って音に安良木がびくっと目を見張る。
反射的に振り向いた先には俺たちも通ってきた最後の入り口の閉ざされた姿。
俺が再度口を開こうとするより早く、今度は体育館の中の電気が一斉に消えた。
「きゃっ」
それは多分、安良木の声だった。
直後に誰かが暗闇で俺に抱きついてくる。
一瞬、寿樹か!?(あの馬鹿ならやりかねん)って身構えたけど、違う。腕を掴むてのひらは細くて小さかった。寄せられた身体も俺の顎ぐらいしかなく、やわらかい。
安良木だ。
寿樹だったらぶっとばせばいいけど、相手が安良木な場合はとにかく対処に困る。安良木が面白がるもんだから、さっきみてーに遊ばれちゃうんだけどさ。
でもさすがに止めてくれよ、こういう真っ暗な中で抱きつくのは。
いろいろシャレんなんねーよ。
駅前の時と同じく、成す術もなく硬直した俺の頭上にいきなり光の道が出来た。
えっ?て思って首だけ巡らすと、後ろの壁の一階と二階の真ん中の辺り、そこにガラスの張られた小窓があった。そこからビームのように一直線に光が伸びていく。耳を澄ます必要もないくらい、はっきりとぢーっていう映写機の音が聴こえてくる。
まばらな拍手が何処からともなく沸き起こって、高い天井に吸い込まれていく。
やっぱ映画だったんだ。
あ〜あ、始まっちまったよ。
やべえなぁ、出るにしたって、出て行きにくいなぁ、これ。
どうしようか考えてると、不意に二の腕を掴む力が強くなったから俺は慌てて曲げていた首を戻した。映写機の真下辺りに立っているおかげで完全な暗闇ではなくなっている。俺の身体にくっついているのは、やっぱり安良木だった。
声をかけようとして、俺は眉を顰めた。
なんだか。
様子が変だった。
どうせまた冗談で抱きついてるんだ、って思ってたのに。
なのに、なんだかその身体が小刻みに震えているように見える。
俺は小さな肩に手を伸ばした。
闇の中、俺は囁く。
「ラギ?」
「ごめんなさい、私、で……」
安良木が。
全部を云い切る前に指から力が抜けた。
がくりと唐突に膝が折れる。
「ラギッ!」
俺は咄嗟に腕を差し出し、状況も弁えず叫んでいた。
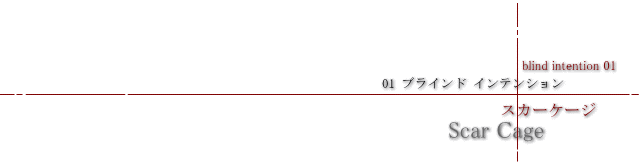
1998年、11月7日。
それが
俺の最も長い10日間の始まりだった。
|