|
「ありがとう」
泣き笑いみたいな笑顔が心臓に突き刺さった。
ありがとう、って何だよ。
俺はお前に酷いことばかりしたのに、なんで礼なんか云うんだよ。
の身体が風に攫われるように揺れた。右手がぴくりと動いたが腕を伸ばす前に気付く。は別にふらついたんじゃない、ただ一歩下がっただけだ。初めの頃、田島に押しかけられる度によくしていたように距離を置いただけだ。
身体の動きに合わせてふわりとスカートが広がる。踵を返した背中の上で長く伸びた髪が踊った。
華奢な肩が遠ざかっていく。
その背中を引き止めたい。強烈に、そう思った。
俺はまたこれが最後のチャンスなんじゃないかと自問する。今まで何度も何度も同じことを問いかけてきた。
だが、今日も同じだった。
俺は陸の上で溺れる。咽喉に鉛が詰まったように声が出ない。シャツが手摺に溶接されたみたいにびくともしない。足には見えないいばらが雁字搦めになっていて動かせない。そんなものは全部云い訳で単に俺が卑怯で臆病なだけなのは吐き気がするほど解ってる。
の姿がドアの向こうに吸い込まれる。
音もなく呆気なく、俺との世界は隔てられた。
項垂れるとコンクリートが視界に迫ってくる。
「好きだった」
繰り返した言葉はさらに苦さを増していた。
きっとドアの向こうには田島が居る。
肩を並べて階段を下りていくふたりの幻影が見える。
それを消す為に俺は目蓋を閉ざした。
「……俺も好きだったよ」
呟きは虚空に溶けた。
三年間、いつだって俺の頭上には嵐が渦巻いていた。
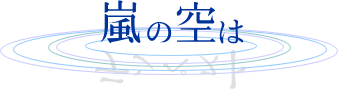 |
のことは最初はむしろ苦手だった。
偶々隣の席になったが、どうも怖がられているくさい。くさいというか割と露骨だった。隣同士で答合わせしろとか、そういうどうしても話しかけなくちゃならない場合でも声をかけると猛獣を見るような目で見られる。こっちだって好きで話しかけているわけじゃないのに、いちいちびくつかれると気分が悪い。つーかぶっちゃけイラっときてた。
が、身に覚えがないどころかそういう態度を取られる原因に俺は心当たりがあった。入学式の翌日だったか、顔を合わせたのなんてまだ片手以下だったのに廊下で田島がいきなり背中に飛びついてきやがった。思いっきり「てめえざっげんな」って怒鳴って、振り落としてやろうと身を捩ったらそのすぐ後ろにが居た。
恐怖に立ち竦む、って表現がぴったりの顔。
目が合ってしまって思わず動きを止めたらその隙に脱兎の如く駆けていった。
なので、腹が立っても俺はに強く出られないでいた。イラっときてもあの顔が脳裏を過ぎって、良心の呵責により苛立ちの炎は消火される。愛想良くしているつもりだが一向にの警戒が解ける気配はなかった。俺は四月だというのに既に席替えが待ち遠しくて仕方がなかった。
それがどうして恋になんか発展したのかっていうと、きっかけは一冊の本だった。
朝錬終えてへろへろで教室に入って、自分の席に着こうとしていたところでの机の上に置かれた栞が目が留まった。
自分も好きな作家の本読んでる奴に対して、本好きってどうして親近感持っちまうんだろう。本好きにしか理解出来ない類の喜びがこのとき俺の頭のネジを緩ませた。俺はとっくに和解を諦めていて、極端な話出来るだけの視界に入らないようにしていたくらいなのに、ついそれ誰々の新刊だよな面白いよなって気安く声をかけてしまった。
はいつものようにびくっと肩を揺らして、俺を見上げて、手の中の本に視線を戻して、もう一度俺を見た。
半分は恐怖、半分は興味みたいな按配の表情で「どうして解ったの?」と微かに首を傾ける。本にはブックカバーがかかっていたし、いくら目が良くても上部に書かれた小さい文字のタイトルなんて俺の位置から読めるわけがない。ただし栞の方は違う。俺は笑ってそれを指差した。答は単純で、その栞はその作家のその新刊用だけの特別デザインだったのだ。
俺の指先から机の上へと視線を移して、三秒くらいかかってからはふわっと笑った。「そっか」と笑って、「花井君もこの人好きなの?」と向こうから訊いてきた。
その顔があどけないっていうか邪気がないっていうか、前日までのがちがちに強張った表情と全然違っていたから俺は内心結構衝撃的だった。そういや普通に女子と話しているときとかはおっとりした感じだったもんなとか、俺は平静を装って返事をしながらそんなことを考えていた。この日は休み時間の間中、俺たちはああだこうだと語り合った。
それですっかり打ち解けて、は俺にびくっとすることもなくなって、お互い本の貸し借りとかするようになった。の親父さんが本好きで、自身も運動するより本を読んでいる方を好むような子供だったらしい。
それでその内、なんていうか、あれ、こいつひょっとして俺のこと好きなんじゃねーの?と思うようなことが増えていった。
例えばだけど、水谷と話していても笑顔なんだけどなんか興味薄げなんだ。でも、俺相手だとどんな話題でも嬉しそうにしている。何より視線が甘かった。視線が甘いとか自分でも意味が解らないが、他に適切な言葉を思いつかない。の身体に詰まっている愛情が目を覗き込むとすべて透けて見えるっていうか、ねだれば何でも許してくれるんじゃないのかって錯覚させるような、そんな目。
けど、この頃の俺はまだに恋愛感情を抱いてなどいなかった。話していて面白いし友人としては好きだけど、彼女にしたいかっていうとそうでもない。性格いいし可愛いとは思うけど、俺の好みのタイプじゃない。女と付き合うって楽しいだけじゃなくそれなりのデメリットがある、それを考えたら別に本気で好きでもないのにと付き合うことはメリットよりもデメリットのが多い。
そんな感じに理性的な障壁に阻まれていて、は俺の心の中心に近寄れずにいた。の存在はその他大勢の内のひとりでしかなかった。
それなのに約三年間にもわたる泥沼の恋愛に俺を引き摺り込んだのは、どうしようもないほど些細な出来事だった。
ペン回し、だ。
もう癖になっていて、俺は手が空くと無意識にくるくるとやってしまう。自分でも気付かない間に毎日くるくるくるくるやっていたんだろう、ある日隣から妙にかしゃんかしゃんと音がした。
何気なく視線を泳がすと、が右手をプルプルさせながら真剣な表情でシャーペンを凝視していた。こいつ何やってんだって思わず見入ったら直後に指の上で半回転しただけでシャーペンが落ちた。
ああ、俺と同じことしたいんだなって直感で解った。
次の時間もプルプルかしゃんとシャーペン落としていて、俺はそれくらいならまあいっかと授業が終わった後「教えてやろっか」って声をかけた。はきょとんと俺を見て、一拍置いてからくしゃりと眉を歪めた。恐れに似たものが背筋を走った。
やばい、と思った。
泣かれるかと思った、それなのには俺の予想を裏切って首まで真っ赤にして両手で俺のシャツの袖を掴んできた。密かに激しく動揺している俺に気付いた様子もなく、愛情と羞恥が鬩ぎあった目で縋るように見上げて「ちがうの」「これは指の運動で」「真似したいとかじゃないから」とか意味不明の弁解をする。
野球でなら何度もあったけど、女相手に目が離せないって状態になったのは初めてだった。指が微かに震えているのに気付いてしまうともう駄目だった。顔が好みじゃないとかもっとはきはきしてるのが好きとか思っていた自分がすげえ馬鹿に思えた。こんな可愛いんだからいいじゃんそれでって、俺の中にあった障壁は見事に薙ぎ倒された。
『何』に今遭遇しているのか解っているみたいに勝手に身体のスイッチが入ったっていうか、体内の血とか筋肉とかが一斉にざわついて暑くもないのに体温が上昇した。頭の方も同じように変なスイッチが入って、昨日までは影も形もなかった独占欲みたいなやつとかシモ系の欲望とか脳内をぐるぐるし始めた。
俺はなんかもうが可愛く見えて仕方ないのと自分の急激な変調が可笑しくて笑いが止まらなくて、そんなことを知る由もないは泣きそうな顔をしてたけど、それも全部ひっくるめてすげー可愛かった。愛しかった。
呆れるほど簡単に俺は恋に落ちた。
コツを教えてやったらその日の内にマスターして、その後、は四日くらいにこにこしながらくるくるしていた。慣れてきた頃に無意識に回しては落としてその度にはっとなって周囲をこっそり見回したりもしていた。一度好きになってしまうと、そのちょっと間抜けな仕草の何もかもがとにかく可愛くて仕方がなかった。
おそらく俺たちは十中八九両思いだった。
それにも係らず俺は告ろうとはしなかった。むしろ俺は自分の気持ちを表に出そうとしなかった。別にビビってたわけじゃない。今となっては完全な言い訳だが、俺が野球部でさえなかったら即行告ってたと思う。野球の存在が俺の決断を鈍らせていた。
二年になるとぼちぼち増えていったが、当時部内に女作った奴はいなかった。女禁止とかそういう部則なんてなかったが、一番しっかりしなきゃいけないキャプテンが率先して、しかも自分から告って新学期早々女作るってそれってどうなんだよ。ナシだろ、普通に考えて。ただでさえ上はいないし部員は十人しかいないっていう、一回緩んだら再度締めるのがすげえ難しそうな環境なのにさ。
俺は自分から進んでキャプテンやりますって名乗り出たわけじゃないけど、引き受けたからにはきちんと責任を果たしたいし、その為には自分がみんなの規範となるべきだと思っていた。せっかくチームとしていい感じに纏まってきてるのに水をさすような真似をしたくなかったし、あいつにとって野球ってその程度のものかって目で見られたくはなかった。
俺は田島に負けたくなかった。
田島悠一郎は間違いなく天才だ。上手い奴は何人も見てきた、でも田島の場合は上手いとかそういう次元じゃない。あいつは打つといったら打つ。あいつだけ魔法の杖を使っているみたいに、いとも簡単にピッチャーの球を撥ね返す。俺はネクストバッターボックスで格の違いってやつを嫌というほど見せ付けられた。
中学時代の俺はキャプテンで四番でチームはそこそこ勝った。俺は野球ってこんなもんだよなって思い上がってもいたし、そのくせ甲子園とか行く奴らはどうせ選ばれた特別な人間なんだろと自分の器に冷静に見切りをつけてもいた。
高校は別に野球部じゃなくってもいいっていうのは本心だった。中学のときの未熟さは未来への逃げ道でもあった。高校に上がったらもっと打てるようになるんじゃなかって何の保証もない希望が持てた。けど、実際に高校生になってしまえばそうはいかない。高校野球は甲子園って形で誰の目にも明らかな答が出る。高校でも野球を続けたら、敗退っていう露骨な形でもって己の限界が見える瞬間がやってくる。壁を見上げて乗り越えられないと認めてしまったときに襲ってくる絶望。一生懸命やったのに届かなかったときの虚無感。そんなもの俺は味わいたくなかった。だから野球を本気でやるつもりはなかった。遊びの、誰が見ても甲子園には行けないようなチームで十分だった。負けたことを悔しいと感じてしまうような中途半端の強さのチームはいらなかった。だから西浦に来た。俺は逃げていた。
なのに、田島は違う。
あいつは甲子園に行くことを夢だなんて思っていない。
本気っていうのとも違うんだと思う。自分がいるから行けると驕っているわけでもない。そういうんじゃなくて、当然っていうのか自然っていうのか、一年生十人しかいなくて女が監督やってるチームでも、高校野球やってるなら甲子園目指すのは当たり前のことだって感覚なんだろう。それが恐れ多いことだとか恥ずかしいことだなんてこれっぽっちも考えていない。俺的には野球経験者だからこそ軽々しく甲子園目指してますなんて口に出来ないのが普通の感覚だと思ってたのにさ。
俺は田島に出会えたことに感謝している。才能の差に頭をバットでぶん殴られたような衝撃を味わった。悔しいと思った。悔しいと思えたことで目が覚めた。挫折するくらいなら楽で向上心の欠如した道を選ぼうとしていた自分を恥じた。恥じれる程度には残っていたなけなしのプライドが俺を奮い立たせた。
田島のようにおおっぴらに口にすることは出来なかったが、メントレの成果なのか、あれほど遠くに感じていたはずの甲子園が頑張ればどうにかなるんじゃねーのかと俺もいつの間にやら思い始めていた。
でも、田島に連れて行ってもらうのは嫌だった。
俺は田島と競おうと決めた。田島におんぶに抱っこするんじゃなくて、きっちりバッティングで貢献して、胸を張って甲子園の土を踏みたい。
その為には野球に集中したかった。田島に肩を並べるとかそれは大それた野望かもしれないが、
追いつくことを諦めたくはなかったし、死んでも喰らいついていく、そういう気概で俺は毎日練習に取り組んでいた。どんだけが好きだろうと、俺は精神的にも肉体的にもいっぱいいっぱいで楽しく男女交際出来るような状態じゃなかった。
だから、あわよくば現状維持のまま引退まで過ごしたいとか考えていた。の視線はいつだって甘くて、が心代わりする可能性なんてこれっぽっちも見当たらなかったし、惚れられているって自信がいつでも自分が望めば状況を動かせるんだという高慢な余裕を生んでいた。
そういうの気持ちを無視した自分勝手で都合のいい考えへの罰だったのかもしれない。
おそらくあれが一番初めの小さな罅だった。
購買の横の自販機のところでと話しているときだった。はないーって例の大声で田島が俺を呼んだ。走り寄ってくる田島の向こうには泉と三橋の姿もある。ああ、あいつらもジュース買いにきたんだなって考えるでもなく思って、俺は田島の飛びつきに備えて身構えた。なのに、田島はにって笑うと「はないーっとみせかけてこっちでしたー!」とふざけたこと抜かしながらに抱きついた。ひっ、って息を詰まらせたの手からバナナオレが落ちる。
俺もも凍りついちまって声も出なかった。
の肩に顎を載せていた田島がどんな顔をしていたのかは憶えていない。は零れ落ちそうなくらい大きく目を見開いていた。俺はどうすればいいのか解らなかった。
膠着状態を破ったのは泉だった。ばりっと音がしそうなくらいの勢いで田島を引き剥がすと、「そういうことが許されるのは幼稚園まで!」と叫んでウメボシ喰らわせた上、田島のポケットから勝手に小銭を奪うとそれでバナナオレを買い直しての手に握らせて、まったく反省した様子もなく「じゃーなー」とかへらへらしている田島を引き摺って帰っていった。はおろか同じ野球部の俺まで一言も口を挟めず呆然と見送るしかなかった。田島は嵐のようだった。ふらっとやってきて好き勝手蹴散らして去っていく。
田島はその後も何度かに抱きついてきて、その度に怒ったが全然効果はなくて俺は頭を痛めていた。は迷惑そうだが一応は許してくれる、でも、これが他の女子だったらそうはいかないかもしれない。田島が謹慎とかマジでシャレにならない。自分の好きな女に他の男が抱きついているのもいい気分はしない。前日にしつこく云い聞かせて漸く約束させたのにあっさりそれも破られた。どうやったら田島に止めさせることが出来るのか、俺はあの日も考えていた。
おめでたいことに俺は『田島はを好きだから抱きついている』という、至極単純な図式をそのときがくるまで見落としていた。
安穏とした俺との関係が壊れるなんてこと、これっぽっちも想像してなかった。
教室で、グラウンドで、街角で、その声は何度となく俺の耳に甦った。
『俺のこと好きだから! お前とんなよな!』
田島は鮮やかに宣言した。
周囲からの注目なんて感知せず、ただ真っ直ぐに揺るぎない目で俺を射抜いて。
俺は、なんで俺なんだよと思った。
馬鹿みたいに突っ立って田島を見返すことしか出来ないままなんで俺なんだよと思っていた。
何故、俺に云うんだ。俺はと付き合っているわけじゃない、第一盗るなって彼氏の台詞だろ、は俺のことが好きなんだからどっちかっていうと俺のがまだ口にして違和感のない台詞のはずだ。田島が何を考えているのか解らなかった。田島の行動に脈絡がないのはいつものことだったが、輪をかけて理解不能だった。が好きなら普通にに好きだって云えばいいはずだ、なのに何故俺に盗るななんて云うんだ。
まさか俺の気持ちがバレているのか?
その考えに指先が冷たくなっていった。
は田島に肩を抱かれたまま俯いてしまっていた。田島はちょっとぞっとするほど真剣な目で俺を見詰めていたが不意に視線を逸らした。に何か囁く。は一度逃れようとして阻まれ、強張った顔で笑おうとして、そして最後に絶望の欠片を目の前に突きつけられたかのように静かに表情を消していった。
そんなを見て、田島はそっと肩から手を退けた。身軽にから離れると「じゃあな!」とさっきまでの鋭さが嘘みたいな笑顔で教室を出て行く。
自分の席に戻ってくると、は無表情のまま鞄に荷物を詰め始めた。その機械のような動きに俺はますますどうすればいいのか解らなくなって謝罪を口にした。自分でも何の為の謝罪か解らなかった。はすうっと視線を上げ、俺を見た。窓が閉まってしまったかのように、の瞳からは何も読み取れなかった。いつも俺に向けられていた好意すら見当たらない。人形のような目で黙って俺を見詰めていたかと思ったら、俄に震えだし鞄を掴むと身を翻した。
俺は後を追わなかった。追えなかった。心配だったがキャプテンという立場上部活をほっぽりだすわけにはいかなかったし、彼氏でもない単なるクラスメートがの後を追いかけるなんてことはもっと出来ないことだった。
田島はいつも通りぎゃーぎゃー騒ぎつつ真面目に練習をこなしていたし、俺もなんでもない顔で指示を出してその日の練習を終えた。
みんなと別れ、風呂入ってメシ食って、いつものように泥のような眠りに飲み込まれる寸前に俺は漸く気が付いた。
田島のしたことは無風地帯に嵐の塊を投げ込んだようなものだったということを。
時々めちゃくちゃ憎たらしいが田島は友達で同じ野球部だ。その田島がに明確な好意を示した。それなのに今更俺がを好きだって口にしたりしたら非常に不味い状況を引き起こす。四番とキャプテンがひとりの女取り合ってるとかどんだけ気まずい部活だよ。俺とが付き合うことになったとしても田島がに惚れてるってのは既に部内に知れ渡っている。どの道気まずい、周りのやつらだって気を使うだろう。そもそも俺は友達と女のことなんかでぎくしゃくしたくない。
だが、平穏に過ごす為の選択肢はひとつだけ残されている。
簡単だ。
俺が口を噤めばいいのだ。
翌日、人の気も知らずに田島は元気一杯だった。
こっちはいつもより睡眠時間が足りなくて疲れが抜けてないっていうのに、朝練後の教室への移動中、何故かわざわざ俺の横に来てデカイ声で水谷とはしゃいでいた。それだけでもげんなりさせられていたのに、田島は平然とした顔でウチのクラスのドアを潜った。当然、クラスの連中はわあっと囃し立てた。憂鬱そうな表情のもこっちを見た。俺はがちゃんと来ていたことにまずは胸を撫で下ろしていたというのに、その元凶である田島はあっけらかんと野次に答えたりしていた。頼むから悪目立ちするような真似は慎んでくれとしゃがみこみたくなった。そんな田島を引き連れた状態での隣の自分の席へと向かわねばならない俺は胃の痛む思いだった。
気まずかったが、挨拶をするとは返事をしてくれた。昨日の人形のような無気力な様子が気懸かりだったので、俺はがわりと平気そうな顔をしていることに心の底から安堵した。
田島の相手はに任せて、俺は自分の机に荷物を移す作業に取り掛かった。とりあえず俺はこれまで通りに振る舞うつもりだった。
要するにとは友達のままでいるってこと。
今後田島がにどう出るのかは解らないが、俺自身はに気持ちを伝えないままでいることに変化はない。もともと三年間そう出来たらと思っていたくらいだし、田島には悪いがの性格を考えたら告られたからって靡くような奴じゃない。田島と俺との三人が同じ大学に行くとは思えないし、高校を出ちまえば俺とが付き合い始めたとしても、その頃には田島にも新しく好きな奴が出来ているだろうし、ああそうなので終わる話だろう。公明正大なやり方ではないかもしれないが、他に良い方法がないのだから仕方がない。
前夜、田島の落とした爆弾の効果に気付いたときは青褪めさせられたが、何てことはない、ある意味俺の希望通りなんだ。これまでだって出来ていた。簡単なことだ。
そんなふうに俺は楽観的に考えていた。
隣で椅子が耳障りな音を立て、らしくないその粗野な仕草に俺は視線を上げた。がいない。俺から見て斜め前の席に跨って座っていた田島がこっちを見ていた。
「田島君なんて嫌い。近寄らないで」
シャツが引っ張られるような感覚の後に背中に温かいものがくっついてきた。嫌悪じゃなくて、むしろ逆の意味で鳥肌が立った。
一旦静まっていた教室がまた沸いた。好奇の視線が突き刺さる。
喜んでいる場合じゃないと、俺は咄嗟に振り向こうとしてに肘鉄喰らわせそうになって慌てて静止した。
「ちょ、、おま」
困っているって顔を作りながら、俺は本気でを振り解けずにいた。どうすっかと思って何気なく顎を上げて正面から田島の視線とぶつかった。
その目に身体が強張った。
睨まれているわけじゃない、田島は真っ黒い目でただ俺を見ていた。それなのに俺の気持ちも姑息な策略も何もかも見透かされているんじゃないかと思わせるような何かがその目にはあった。
結局、泣き出したを篠岡が保健室へと連れて行ってくれた。俺はまた空虚な謝罪を口にした。
小さな背中を見送りつつ、俺は自分の考えがあまりにも甘かったことを思い知らされていた。わりと平気そうだなんてとんでもなかった。
現状維持で俺はいい、でもは無理なのかもしれない。
が泣き出した理由が俺にはいまいち理解出来なかったが、もともとは田島のことが苦手っぽかった。田島は嫌いだと口にしたり俺の背中に抱きついてきたのもらしくなかった。人の都合も考えずがんがん攻めてくる田島に好かれるってのはにとっては相当のストレスなのかもしれない。
俺は野次に怒る気も起きず、適当にあしらって席へと戻った。
は午前中保健室に行ったままだった。一限が終わって篠岡に訊いてみたら熱があるから寝てるって話だった。気にはなったが俺はやっぱり保健室に様子を見に行くとか、これ以上ゴシップネタを増長させるような真似をする度胸はなかった。
昼休みになってやっと姿を現したは朝よりも少しばかり赤い顔をしていた。声をかけると微かに笑う。その笑顔に少しばかり気が休まった。俺は隣にがいない間、どうすればいいのかずっと考えていた。だが、どこもかしこも丸く収まるような、そんな夢のような方法はないことに改めて落胆させられただけだった。一番マシだと思えるものはやっぱり俺が昨夜考えた通り、このまま現状維持で三年間をやり過ごすことだった。
俺はそれで大丈夫だ。
でも、は?
熱が出たのと田島の告白に因果関係があるのかは判然としないが、調子の悪そうなの姿は物凄い勢いで俺の心を揺さぶっていた。
俺は女のせいで友達と争うような奴を馬鹿だと軽蔑していた。どうやったら友達より女の方が大事だって思えるのか謎だった。俺は絶対そんな無様なことはしないと決めていた。もしそんな状況になったら女の方をすっぱり諦めて友達を取る、そう思っていた。
なのに、今まさに俺は田島を裏切ろうとしていた。
最高に浅ましいことを考えてしまったのだ。を共犯者にすればいい。俺がを好きなことも告白出来なかった理由も全部正直に話せばきっとは解ってくれる。その上で表向きは友達のまま隠れて付き合えばいいのだ。田島が変わらずを追いかけてきたとしても俺がいればはこんな顔しなくてすむんじゃないかっていう根拠のない自信があった。
これはの為なんだと美しい毒が全身に広がっていく。一旦思いついてしまうと一刻も早くそうすべきなんじゃないかと、俺はそのみみっちい考えに流されそうになっていた。実際半分以上流されていて、が口を開くのが後一秒遅かったなら俺は話を切り出していただろう。
「あのね、これ、田島君がくれたみたいなんだけど、私今飲めそうにないから貰ってもらえる?」
「田島が?」
田島の名前に心臓が縮み上がる。まさに冷水を浴びせられたって感じだった。じわりと苦いものが込み上げてきた。あまりにも深い自己嫌悪に顔を歪めそうになって、それはどうにか堪えたが眉間に皺が寄ることまでは止められなかった。
自分が口走ろうとしていた内容はもちろん、俺は田島がのもとを訪れていたことに少なからぬ衝撃を受けていた。
田島は行ったのか。
俺は行かなかったのに。
俺だってのことが気掛かりだった、でも朝のことがあるし俺がわざわざ見舞いに行ったりしたらいらぬ注目を集めてしまい余計の迷惑になる、そう考えた。
田島は俺と違って人の目などこれっぽっちも気にしない、だから平気な顔で保健室にも顔を出せたんだろう。そう切って捨ててしまうことは容易いことだけど、本当にそうだろうか。それだけだろうか?
「どうかした?」
「ああ、いや」
俺はの小さな手から紙パックのジュースを譲り受ける。妙な沈黙を作ってしまったことを適当な言葉で誤魔化しながらも俺の脳裏には田島の影がちらついていた。俺の手の中で回転するジュースは今の俺そのものだった。嵐に飲まれたように思考が空転して定まらない。田島は何を考えているか解らないが悪い奴じゃない。多分、っていうか絶対俺の気持ちなんて知らないはずだ。あいつがそんな人の恋愛感情の機微に聡いわけがない。どうせ昨日の盗るな発言だって俺がと仲がいいからとか、そういう子供染みた理由なんだろう。
手の中で回転が止む。
覚悟を決めるつもりで俺は机にそれを置いた。
は俺を見ていた。腹をくくったはずなのに俺の中で善良さと狡猾さが拮抗する。善良さが勝った瞬間に口を開くも、俺の舌は重く鈍かった。
「あのさ、あんま田島のこと嫌わないでやってくれねーかな」
やりたいことしかやりたがらない田島が見舞いの品まで携えて自主的に様子を見に行くんだ、あの性格だから気紛れを起こしただけなんじゃないかと俺は疑っていたのだが田島は真剣なんだろう。田島は本気でのことが好きなのだ。それを考えると嫌いと云われてしまう田島がなんだか可哀想になってしまった。ただしが田島に本当に心を動かすような事態になったらそれこそ今度は俺が困る、だから口にするのに二の足を踏んだ。虫がいい話だが好きにならなくてもいいから友達として仲良くというか、避けたりしないでやって欲しかった。
あるいは俺は償いのつもりだったのかもしれない。田島を出し抜こうとした代償に田島の為になんかしてやる、そうすることで自己嫌悪から脱したかったのだろう。俺は自分のことしか考えてなかった。
俺はの気持ちを考えてなんかいなかった。
大きく目を見開いたは明らかに傷ついていた。身を硬くして全身で俺の言葉を拒絶していた。
俺は自分がどれだけ残酷なことを云ったのか、結果を突きつけられたことでやっと理解した。慌てて取り消しにかかった俺の言葉をは遮った。いつだって俺の話に嬉しそうに耳を傾けていたがそんなことをするのは初めてのことだった。
「止めてよ、私は」
予感が胸で跳ねた。
云うな、と思った。
それを聞いちまったら面倒なことになる。
まるで俺の声が聞こえたみたいには唇を閉ざした。すうっとの顔から感情が抜け落ちていく。また人形のような無機的な表情を浮かべ、は俺に向かって伸ばしかけていた腕をゆっくりと下ろした。
なんでもない、とは云った。だが、なんでもなくなんてないことは俺もも解っていた。痛いくらい解っていたけど、俺は何をどう伝えればいいのかが解らない。
チャイムが鳴った。俺たちは互いから視線を外した。
放課後、と話をするべきかどうか逡巡している内に水谷に呼ばれてしまい、俺は結局何も云えずに教室を後にした。
田島は例のデカイ声で篠岡にの様子がどうだったかを尋ね、篠岡は部室に来る前にどうやらに声をかけていたようで、田島の質問にも嫌な顔ひとつせず答えていた。
その田島はちょっと目を放した隙にいつの間にか姿を消した。一時間近く雲隠れした理由をモモカンに問われ、「負け試合濃厚だった勝負を九回裏フルカウントで同点にして延長戦に持ち込みました!」などと意味不明なことをほざいて力一杯金剛輪を喰らっていた。巣山あたりに何してたんだよと半ば呆れ口調で訊かれても、「だからウンメイ相手に試合してきたんだよ」等と要領を得ないことを云うばかりで、田島が何をしていたのか最後まではっきりしなかった。
翌日は休んでいて、俺は胸騒ぎというか、あの空白の時間に田島がまた何かしたんじゃないのかと憂慮を抱いていた。
さらにもう一日空席は続いた。明くる日、自分の席の隣にの姿を見つけて俺はどきりとした。俺の背後には田島がいた。日課のように後を付いてきていた田島が俺の横から教室を覗き込む。
「ー!」
止める間もなく田島が俺を追い越していく。何食わぬ顔で教室に入りながら、俺は早歩きにならないよう細心の注意を払った。本当は走りより田島の首根っこを捕まえたかったが、今俺がそれをやったらキャプテンだからというより田島に嫉妬しているように見えるんじゃないかと思えて手が出せなかった。
「おはよー。もういいのか?」
が頷くと田島は破顔した。片手で俺の椅子をがたがたと引き寄せて勝手に腰を下ろす。
「そっか。じゃあさ、海いこーぜ、夏になったら」
「やだ」
「ええーなんでだよー。俺、の水着みてーよー」
「私、あんまり泳げないから海なんて無理」
「浮き輪使えば大丈夫だって。それに俺、が溺れないようちゃんと見ててやるからさ」
「沖に流されているのに本当に見てるだけで助けてくれなさそうだから嫌。おはよう、花井君」
が俺に笑顔を向けてきた。田島を避けて机の上に荷物を置きつつ、どうやってさりげなく田島をから引き剥がすかを考えていた俺は朗らかな笑みに面食らった。
「…おう、おはよう」
「なーなー行こうよー」
は俺を見上げて穏やかに目を細めた。それ以上は何も云わずに、田島へと視線を戻した。しつこく行こう行こうと繰り返す田島に対して、行かない絶対行かないと声を荒げるわけでもなく淡々とにべもない返事をは繰り返す。
なんていうか、気味が悪いほど自然だった。
泣き出したあれは幻だったのかと思うほど、は田島に普通に接していたし、そんなに田島の方も何の違和感も感じていないようだった。
俺だけ取り残されたような焦りを覚えた。安泰だと呑気に構えていた足元が急速に揺らいでいくような感覚。いや、俺はそもそも揺れていた。は好きな奴で田島は友達で、どちらも切り捨てられない俺はその場その場でころころと意見を変えた。田島を憐れみあいつを嫌わないでくれと云うことでを傷つけたくせに、今度は田島と係わると情緒不安定に陥るようだからとから田島を遠ざけたいと考えていた。まったく一貫性がない。矛盾している。だが、並び立たないはずの俺の望みが実現していた。
今現実に俺の目の前で田島はと仲良くやっていて、は田島に怯えていない。
田島とは俺の思惑なんて飛び越え、俺の与り知らぬところで折り合いをつけていた。俺が望んだ通りになっているはずなのに、満足感どころか戸惑いばかりが降り積もる。
何か大きな過ちを犯したような気がした。
俺は何をやってるんだ?
足元から寒気が這い上がってきた。大きな不安が胸の中心で渦を巻き始め、世界の輪郭が歪む。吹き荒ぶ暴風に揺れて捻れて歪んでいく。
俺はその幻想を振り払う為に拳を握った。
隣でが田島の言葉に笑う。俺は酷く驚き、それで漸く気が付いた。
振り払うどころか、とっくに何ひとつ俺の思い通りにならない嵐に頭上を覆い尽くされていることを。
その日からは田島を拒絶しなくなった。
けれど、それは田島のことが好きだから受け入れたようには見えなかった。
俺と話していて『嫌だ』なんて言葉をは使ったことがない。なのに、田島と話しているときのは容赦なく嫌だと口にした。ずばずば遠慮なく切り返すし露骨に眉を顰めたりもしていた。それでもが纏わりつく田島を疎ましく思っているようには見えなかった。むしろ率直な物言いの分、と田島は親密に映った。
ただしの目は常に俺に向いていた。
どれほど距離が縮まろうと、が田島にも俺に向けるような甘い眼差しを向けることは絶対なかった。
二年になると、俺も田島もとはクラスが別れた。と同じクラスになった水谷の話によると、田島はわりと頻繁に教室に顔を見せていたらしい。表向きはただの元クラスメートでしかない俺にそんなことが出来るわけもなく、このまま接点がなくなるかと危ぶんだがそうはならなかった。
昼飯時に野球部で集まっていると田島がを引っ張ってきて、どういうわけか必ず俺と田島で挟むようにを座らせた。放課後や試合にもは田島が呼べば姿を見せた。
田島が何故わざわざそんなことをするのか俺には解せなかった。田島はの気持ちに本当に気付いていないのだろうか。あれだけ傍にいて気付いてないならいくらなんでも鈍すぎたし、気付いているなら愚かにも程がある。
それでも田島は相変わらずへの好意を隠そうともしなければ、恥ずかしげもなく大声で好きだと叫ばれてもは知ってるよと笑うだけだった。
その内には時々篠岡の手伝いをするようになっていった。は田島を介して野球部と接点を広げていった。俺も変わらずが好きだったが、部内で『は田島の想い人』という認識が高まるにつれ、自分の気持ちを周囲に察知されてはならないという思いから俺の態度はむしろ素っ気なくなっていった。
だが、何人かは気付いていたと思う。の目がグラウンドのどこに注がれているかを。
試合を見に来たとき、は外野席ならセンター付近、内野席でも外野寄りが定位置だった。田島の応援にきているにしてはちょっと不自然だったかもしれない。
実際、俺に近付く為には田島を利用しているっていう、非好意的な噂が部内にはあったようだった。二年の夏の終わり頃だったか、いつになく集中力がなかった後輩にその理由を辛抱強く問い質すとその噂のことを白状した。田島信者というくらい田島に懐いていたその後輩は、にいい感情を持っていなかった。それで、どうやら田島に向かってさっさとキャプテンに告白して振られてくればが田島の方に擦り寄ってくるんじゃないか的なことをつい口にしてしまったそうだ。すると田島はすうっと表情を消して『お前には関係ないだろ』とまっすぐに後輩を射抜き、聞いたこともないような声で『俺がに勝手にくっついてんだ。のことなんにも知らないくせに関係ない奴が解ったふうなこと云うな』と吐き捨てて謝罪する暇さえ与えず去ってしまったらしい。
後輩相手でも田島の突拍子もない振る舞いはそのままだったし、怒るときも田島はでかい声で何が駄目かをはっきり口にした。だから余計に静かに怒りを湛えた田島の態度が後輩には堪えたのだろう。涙目の後輩を宥めつつ、俺は内心驚きを隠せなかった。田島がきちんとを守ったのが意外だった。いや、意外でもなんでもなかったのかもしれない。
確かに俺の目から見ても田島との関係は酷く不均衡なものに思えた。一方的に田島が好意を与えるだけで、は田島を突き放すことも受け入れることも選ばない。俺はそんなが理解出来ないでいた。
三年になってもが俺を見る目は相変わらず甘かった。田島は誰に告られても全部断ってにべったりで、それを見て俺はいよいよから距離を置くようになった。は田島といて本当に楽しそうに笑うことが多くなった。俺と疎遠になる代わりに、と田島は心の距離まで近くなっていっていく気がした。俺は焦りを覚えていた。
も田島も抱える想いに揺らいだ様子はなかった。なのに、俺は苦しかった。誰にも云えずに抱えていることが苦痛だった。それでも、叫ぶことも捨てることも思い切れずにいた。
考えすぎて自分が本当にのことを好きなのか解らなくなったこともある。
田島が欲しがっているから渡したくないだけなんじゃないのか、そう迷ったこともある。
ただ見ていないで、が好きだと云ってくれればいいのにと卑怯なことを考えたこともある。
俺は現状維持で大丈夫だと思っていた。
それなのに、俺の方が大丈夫ではなくなっていた。
激しく荒れ狂っている空がどんどん堕ちてきて、三人だけが閉塞した空間に押し込められていくような息苦しさに窒息しそうだった。まるで悪魔の悪戯のようにと二人だけで話す機会がある度、俺はいつも真意を吐露しそうになっては毎回口に出来ずに終わった。時が経てば経つほど身動きが取れなくなり、気持ちばかりが重くなっていく。交わらない感情に逃げ場はなかった。
俺は窮屈な箱庭を誰かに破壊して欲しかった。
キャプテンであることの責任感と、田島に負けたくないっていうプライドだけが嵐の中で俺を支えてくれていた。
そして三年の暑い七月、俺が待ち焦がれた箱庭を壊す者が現れた。
息の詰まるような関係を木っ端微塵にしたのは誰でもない俺自身だった。
俺はまた同じ過ちを繰り返したのだ。
その日は練習後、後輩がデジカメで写真を撮っていた。夏大が終われば引退となる俺たちの為にアルバムを作ってくれるという話だった。
鬱陶しいことにキャプテンキャプテンとまたあいつらは人を担いできて、こっちも一枚こっちも一枚と俺はもみくちゃにされた。今じゃ西広や沖よりでかくなった田島は、背中にふたりほど背負った姿を撮られていた。さらに続けて泉に圧し掛かろうとして蹴られる。明日は予選決勝に進めるか否かの大事な試合だというのに、本当に泉も田島も全然成長してなくて俺もげらげら笑った。
その内にひょいとグラウンドの隅に駆けていき、田島はをグラウンドへと連れてきた。二人だけのを撮ってくれとカメラを持っている後輩を大声で呼びつける。それを聞きつけた巣山や水谷が、の肩を抱いている田島の後ろをわざとうろちょろする。あっちいけよと怒鳴る田島を俺たちはグラウンドに座り込んで笑って眺めた。
虚勢じゃなく、俺は本当に笑っていた。
俺は田島とがくっついていることにも慣れてしまっていて、もうそれくらいじゃ痛みを感じることもなくなっていた。
何枚も撮らせる田島を誰かがしつけーぞと野次った。また笑い声が上がる。も笑っていた。今度は泉に呼ばれて、カメラを手に後輩が慌しく走っていく。それを見て田島がの耳元に何か囁き、も顎を上げて微笑み返す。
額を寄せ合うようにして笑い合っている二人は、何も知らない奴からすればきっと恋人同士に見えたに違いない。それくらい自然だった。
そんな二人の様子を目にしても俺は羨ましいとも腹立たしいとも感じなかった。正常な感覚は疾うの昔に麻痺していて、陸の上で溺れるような息苦しさだけがあった。それを隠して俺はぼんやりと目の端に二人を捉えていた。カメラが去っても田島とはそこを動かなかった。田島は二年の春頃から一気に背が伸びて、今では俺とそう変わらないほどになっていた。だからと話していると、田島はよく身を屈めていた。最初目にしたときはキスしようとしてるのかと思ってぎくりとさせられた。
周りの目もあるし、俺はこの日も無関心を貫くつもりだった。
だが、不意に田島が不思議そうな顔でを見た。肩から手を外して、何事かを告げた。の笑顔が瞬時に凍りつく。
愚かにも俺はそれを見過ごすことが出来なかった。
思わず顔を向けてしまった。
計ったようなタイミングでもこっちを見た。
視線が絡む。
俺と目が合ったことに驚き大きく瞳を見開くも、はすぐに泣き出しそうに眉を歪めた。今にもその唇は俺の名を叫びそうだった。
俺は咄嗟に目を背けていた。
あんな顔で俺の名を口にしたら誰だって変に思う。ましてや直前まで田島に肩を抱かれて笑っていたんだ、これまで気付いてなかった奴も流石に気付くだろう。解っていてそれでも波風立たないようにさりげなく配慮してくれていた阿部や水谷や栄口の努力が全部無駄になる。先輩先輩って純粋に慕ってくれてる後輩に泥沼の三角関係なんて見せたくない。
俺の所為で部内の結束を乱すような真似は死んでも許されない。
明日は大事な試合なんだ。
頼むから今だけは止めてくれ。
背中に暑さの所為じゃない汗が伝った。俺はへらへら笑いながら横顔に突き刺さる視線をやり過ごした。
やがてそれも消え、しばらく経ってから周囲を見回してみたがの姿はなかった。
最後に円陣を組み、俺はいつも通りに解散を宣言した。
翌日、背中に罪悪感を貼り付けたまま俺は守備位置についた。球場にの姿はなかった。そのことに負い目を感じもしたが、安堵も同じくらい覚えていた。その試合、俺たちは危なげなく勝った。
そして、最後の試合となったあの日。
は俺ではなく田島を見ていた。
あの日からどこで間違えたのか、そればかりを考えていた。
衆人環視の中、を田島から庇うことも出来ずにいたのがいけなかったのか、教室を飛び出したを追い駆けていたら、保健室に見舞いに行っていたら、汚かろうがさっさと想いを告げていたら結果は違っていたのか。
友達の好きな奴だからと遠慮したりせずに、周囲の視線などに怖気づかずに、田島のように欲しいと叫べばよかったのだろうか。
そうしていれば、今、の隣にいるのは俺だったのだろうか。
だが、無理だ。
俺は田島にはなれない。なれるわけがない。
捨て身ですべてを賭けてただひとりを求めるようなことは俺には無理だ。
目を開けるとじわじわと首の後ろの皮膚を焼かれる感覚が戻ってきた。蝉の声が鼓膜に刺さる。屋上には俺がいるだけだった。
熱の塊のような風がシャツの裾を嬲る。
俺は一度もに手を差し伸べてやることは出来なかった。傷つけることしか出来なかった。
それでも俺はのことが好きだった。
穏やかで賢くて、俺を見詰める甘い眼差しが愛しかった。
しばらくはふたりの姿を見る度に心臓が痛むに違いない。
それでも俺の嵐は静かに終わろうとしている。
俺は再び空を見上げた。
嵐の空は、清らかに澄んでいた。
|