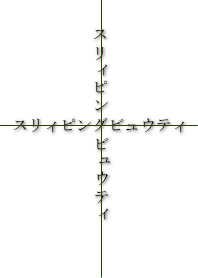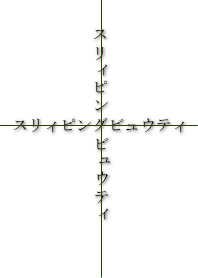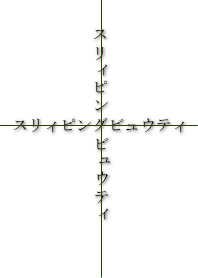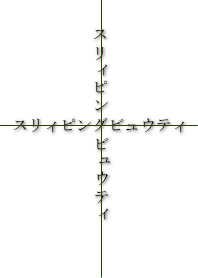という少年に対して私が最初に抱いた印象
それは銀のナイフだった
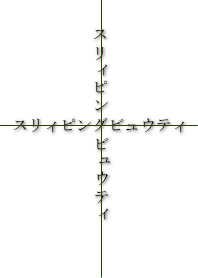
まるで雪に埋もれた真っ赤な椿みたいに、彼らは平凡な教室の中で鮮烈に浮かび上がって見えた。
入学式が終わり、私たちは体育館から振り分けられたクラスへと移動した。
けれど、先生がまだ現れないので誰も席に着こうとはしない。何となく誰もが一番最初に座ることを躊躇って、結局、前や後ろの方にそれぞれ少人数で寄り添うように集っていた。
すると不思議なことに『先生が来るまで着席禁止』と黒板に書かれている訳でもないのに、もし今勝手に席に着こうものなら確実に非難の視線が乱れ飛びそうな雰囲気が醸成されていった。仕方がないので、輪に習って私も窓の傍で馬鹿みたいに突っ立っている。
時間の無駄だから速く先生来ないかしら、と私はがらんとした校庭をぼんやりと眺めていた。
不意にがらりと扉が開く。
やっと先生が来たのかと思って私は振り返った。
同じように思ったのか一斉に視線が集中する中、扉をくぐったのは派手な髪の少年だった。
日に透けると金色と見紛うほどに明るいその色に目を奪われて、続いて僅かに身を屈めるようにして教室に入ってきた少年に目を見張る。
彼の方は標準男子より頭二つ分ぐらい背が高かったのだ。
教室中が唖然として見守っている中、彼ら二人は周囲の注目など綺麗に無視して、さも当然といった顔付きで窓際の一番後ろの席へと腰を降ろしたのだった。
あまりにも堂々としたその態度と容姿の所為で誰もが上級生が来たのだと思ったに違いない。
実際、私も最初はそう思った。
でもちょっと考えてみればそれは変な話で、ちゃんと見てみれば名札の色だって私たちと同じ学年のものなのだ。
上級生が入学式早々に何事かと引き攣った顔で黙り込んだクラスメートたちも、それに気が付くとひそひそと言葉を交し始める。
この中学校は近隣の複数の小学校から生徒が集まっているという話だった。あだ名や下の名前で呼び合っているのが時折漏れ聴こえるので、それぞれ顔見知りの同窓の子達が集まってグループを形成しているのだろう。
けれど、その二人組みと同窓の生徒は居ないのか、クラスメートの誰も彼らに話し掛けようとはせず、ただ小声で何事かを囁きながら遠巻きに眺めている。それはどちらかといえば感じの悪い行為だった。どうも彼ら二人はその派手な外見と攻撃的な空気に加え、暗黙のルールの違反という三重苦で速くもクラスメートの過半数の反感を買ったようだ。
私はと云えば引っ越してきたばかりのこの身で顔見知りの子が居るわけもなく、誰と口を利くでもなしに他人事のように教室の微妙な空気を眺めていた。
誰もがどうしたわけか声を殺して会話をしている。
入学式、という晴れの舞台のはずなのに、いっそ滑稽なほどの重苦しさが漂っている。
私は原因をちらりと盗み見てみた。
一番後ろの席に黒髪ののっぽさん。
彼は少年と呼ぶのを躊躇うほどに背が高い。この間まで小学生だったとは思えないほどしっかりとした体躯をしている。
一見して穏やかそうな表情をしてるのだけど、その身体つきの所為で近寄りがたい印象を周囲に与えていた。
そして、その前の席には蜂蜜色の髪の少年。
蜂蜜のような色艶の髪を持つ、綺麗な少年だった。
鮮烈な印象の目元と細い顎、髪と同じで色素の薄い肌と瞳。その淡い色彩は華奢な身体つきと相俟って中性的な容姿に良く映える。
けれどその繊細な造作に反して、彼の方が非友好的な空気を撒き散らしているのだ。
それどころか、時折きつい眼差しで囁きを交わすクラスメートを睨み付けていく。これでははっきり云ってクラス中に喧嘩を売っていると思われても仕方がないだろう。
何故そんなことをしているのかは知らないが、教室の空気の悪さは彼が原因だと云い切っても差し支えがない。
だが、もう一人の方はそんな片割れの態度を諌めるつもりは全くないようだった。彼はにこにこしながら不機嫌そうに眉間に皺を寄せた片割れを眺めている。むしろ自分たちが異分子として浮き立つことを楽しんでいるような表情だ。
私は窓の外に視線を戻して小さく溜息を吐いた。
厄介なクラスに配属されたのかもしれない。
「スガ!!」
湿っぽい教室に突然無遠慮な声が投げ込まれ、数分ぶりの大きな声に私は思わずびくっとなる。振り返ると他の子も同様に驚いた顔で出入り口を注視してる。
先頭に居たのは見事な坊主頭の男の子で、それ以外は標準的な外観をしていた。皺の無い学生服が彼もやはり新入生だということを教えてくれる。
その彼が件の二人組みに笑顔を向けていた。
「やっぱこのクラスか」
そう云ってずかずかと教室に入ってくる。
人懐っこい笑顔で向かう先はやはりあの二人のところだった。坊主頭の彼の後にもさらに数人が続く。それぞれ個体差はあるものの、クラスメートの大抵の子が怪訝そうな顔をしていた。気持ちは解る。素朴な印象の坊主頭の彼があの苛烈な少年のお友達、というのはいまいちぴんとこない。
「お前らのクラスってほんとにスガとしかいねぇんだな、ウチのガッコの奴ら」
坊主頭の少年から蜂蜜色の髪の少年に視線を戻して私は思わず目を丸くした。
恐い顔をして周囲を牽制しまくっていた彼がふわっと幼げな表情になって笑ったのだ。
「どうせあのセンコーから報告でも云ってんじゃねぇの?俺たちを孤立させた方がいとかさ」
「違うよ〜。それなら僕と君をまず分断させるんじゃないの〜?」
「いや、俺なら須釜が止めないとがより暴走するからセットにするな。あながちほんとに福田がチクったんじゃねぇ?」
「俺が暴走って何だよ、ざけんな、マツ」
そう云ってまた笑う。
その後もさらに何人かがわざわざ彼らの元を訪ねて来た。
不思議な光景だった。
彼らが去ってしまうと、またあのしかめっ面に戻る。また誰かが来ると、素直で裏の無い笑顔を浮かべる。
境界線の激しい人物だ、と私は彼を判じた。
懐に入れた人物には酷く鷹揚に構えるが、それ以外は排除すべき敵らしい。
ずいぶんと極端で潔癖だ。
私にしては珍しいことに、少し他人に興味が涌く。
結局入学式から三十分ほど経過してから漸く担任がやってきて、教室の微妙な空気を読むこともなく、ありふれたお決まりのお祝いを述べ始めた。
私はそれを聴き流しながら、やっと席に着く事が出来てやれやれと脚を休ませていた。本音を云えば私も彼ら同様、適当な席にさっさと座りたかったのだ。椅子が在るのに何故無駄に体力を消耗させねばならないのよ、と思っていた。
ただ私は彼らと違って足並みを乱すような真似はしたくはない。集団行動に迎合する、というよりはそうすることによって生じる面倒を回避したいのだ。
結局、席はとりあえず適当に座れ、という事で彼らは当初確保した席をまんまと手に入れていた。私は窓際に立っていたから、座れと云われて窓際の一番前に座った。丁度彼らの列の先頭の為、彼らの様子は窺い知ることが出来ない。
ぼんやりと中年の担任の濁った声を聞き流していると、やがて自己紹介に話は移っていった。
私の居る列から、ということになり、私は仕方無しに前に進み出た。
「初めまして。蓑本安良木です」
思った通りの反応が返ってくる。
私は自分で可愛げがないなと思いつつ、先手を打って笑顔を作ってみせる。
「可笑しな名前ですが本名です。引越しの都合でこの中学に通う事になったので、小学校の時の顔見知りはいません。どうか仲良くしてくださいね、宜しくお願いします」
まばらに拍手が沸く。形式美以外の何物でもない。
くだらないと思いつつ、私は笑顔に会釈もつけて席に戻った。
隣の席の女の子がよろしくね、と声を掛けてくれる。こちらの言葉は純粋に嬉しかったから、私も笑顔でよろしくねと返した。
私の背後から次から次へと教卓の前に進み出ては、早口にはにかむような自己紹介をして行く。失礼だけど、あまり興味を引くような自己紹介ではない。
三人目が終わると、私の背後でひときわ大きく椅子が鳴った。
ああ、彼か、と背後から強い存在感を感じる。
足早に私の横をすり抜けて教卓の前に立つ。
それまでの生徒が皆の視線を避けるように目線を天井や床に向けていたのに、彼は憮然とした表情で教室中を眺め回した。
「…。趣味サッカー。以上っす」
瞬間、ざわっと空気が踊る。
同時に君の頬が腹立たしげに歪む。
私も人のことは云えないけれど、でもでもだってって女の子の名前じゃない。
ああ、でも、そうか。
私は君の態度に得心が行った。
彼はこうなることを予見して端から不機嫌だったんだろう。髪の色をからかわれるのを厭うている所為かと思ったけれど、それだけじゃなかったのだ。むしろこれまでにも何度も経験したであろう、避けがたいこの反応への予断が彼を苛立たせていたのだ。
君は教室のざわめきを無視して、ひとつ舌打ちすると教壇を降りようとした。
だが、その時無遠慮な声が彼を呼び止めたのだ。
「だってよ。女ならスカートはけよな、髪もイキがって染めてんじゃねーよ」
君が発言者を求め機敏に振り返る。
せっかくの綺麗な顔の眉間に厳しい皺を寄せ、声のした方を睨め付けていく。犯人を発見したのか、その視線が定まる。と、思ったときには、彼は既に自分の席に向けていた踵を唐突に返していた。
「あ、おい」
担任の制止を振り払って、君は無言で奥へと突き進む。教室の空気がみるみる硬化してくのが見て取れるようだった。
廊下側の列の一番後ろ、そこで立ち止まる。一人の男子生徒を見下ろす。
私の席からは引き攣った顔をした男子生徒が丁度よく見えた。
「な、んだよ、オカマ」
さっきの声と同じ声だった。けれど今度の声のが台詞の内容の割には弱々しい。
君はやはり無言で腕を振り上げた。
「あ!」
男子生徒が怯えて両手で顔を庇う。
君は構わずに殴り付けた。
教室に意味の無い悲鳴と喧騒が溢れた。
殴られて倒れた男子生徒の胸倉を掴みさらに殴り、そして蹴り飛ばす。
とばっちりを恐れた周囲が必要のない大声を上げながら机を揺らして逃げる。逃げる生徒が窓の方に殺到しようとするものだから、さらに混乱が生じて机が倒れて余計に騒ぎが大きくなる。
私は椅子に座ったまま、ただその騒乱を眺めていた。
「止めなさい、!」
担任が後ろから羽交い絞めにして、それで漸く君は静止する。……ああ、違う。止まってあげたんだ。振りほどけるのに、振りほどかないんだ。
蹲る同級生を見下ろす君の表情でそれが解った。
暴力を振るったくせに、その目に宿っていたのは暴力に酔った怒りじゃない。
彼は自らの誇りを護ったに過ぎないのだ。
侮辱を許さない事を示す決然とした態度。
これでもう彼の名をからかおうとする者は現れないに違いない。なんて合理的で獣のようなやり方だろう。
けれど、私は野蛮なその行為に僅かに憧れた。そんな真似をしたら周囲から孤立してしまうのに、端から彼はそんなもの恐れているようには見えない。自分を貫く為の物理的な腕力、不条理な屈服を許さない精神的な核心、その両方を彼は持っている。そういう強さが私には羨ましかった。
「、お前は何て事を…!」
声を荒げる担任と君の脇を何ら気負うことなく不意にふらりとのっぽの彼―須釜君が横切って、入学早々ぼろぼろにされた不幸な男子生徒の前へと屈み込んだ。
ぎょっと硬直するクラスメートなんて全然気付いていないみたいに柔和な笑顔を浮かべる。
「大丈夫ですか〜?多分も手加減したはずだから折れてないとは思うけど一応保健室行きましょうか〜?」
にこにこ笑いながらそう云う。
直感的に悟る。
彼ならきっと君を止められたのだ。
でも、それなのに君の気の済むまで殴らせた。
須釜君にとって今日会ったばかりのクラスメートが傷つくより、君の矜持を優先させることの方が大事なことなのだろう。
それを何人のクラスメートが見抜いたかは解らないけれど、本当に恐いのは殴ることを躊躇わなかった君より彼の方だ。
泣きながら呻く少年に肩を貸す須釜君は相変わらずにこにこと笑っている。
私はじっとその笑顔を見つめていた。
入学早々のこの事件は彼らがクラスから孤立するには十分すぎる出来事だった。
特に君の方の。
ここ最近は他のクラスメートとも喋っている須釜君の姿を見かけるようになったが、君が須釜君以外のクラスメートと口を利いているところは未だ見たことがない。須釜君が他の人と話している時は大抵机にべたりとへばりついてつまらなそうな顔で校庭をぼうっと眺めているか、寝ているかのどちらかだった。
人の口に戸は立てられないとは云うけれど、君のあの狼藉の噂は本当に瞬く間に広がっていた。校内で彼の名を知らない生徒は今では居ないだろう、というぐらいだ。
それでも噂が噂なだけに彼はパンダにならずに済んでいた。噂を聴いてそれでも彼を見物に来ようというツワモノは殆ど居なかったが、ただし、その分目的の明らかな呼び出しはあるようだった。
別に彼らと親しくない私でもいつのまにやら知っていたのだ、あからさまに生意気な一年はこういう目に遭うんだという牽制と脅迫の要素が含蓄されて、わざと上級生から流布されているのだろう。
私が聴いただけでもすでに二回も君は呼び出されている。まだ入学式から二週間ちょいなのに、しかもまた近々三回目の呼び出しがある、という話だ。
けれど彼が逃げたとか、彼が負けたという噂は耳にしなかった。事実、君は入学式から一度も休んでいないし、掠り傷ひとつ見当たらない綺麗な顔で毎日平然と登校している。
上級生も無駄な事をする、と思う。
君が誰かに膝を屈する姿など想像できない。
それは私の独りよがりな想像じゃなく、確かな真実だという気がした。
彼は誰にも跪かない。
私は教室の窓ガラスを閉めた。
空にオレンジを滲み始めるような時刻だ、当然教室に人影はない。本当は暗くならない内に早く家に帰らなくてはならないことは解っているのだけど、私は人の居ない学校というのが好きで、時折こうして誰も居ない空間を独り占めしたくなるのだ。
生徒の消えた教室というのはとても広々としている。遮蔽物が在るか無いかで同じ面積でもずいぶんと印象が変わるものなのだ。同じように黒板の比率さえ違って見えるし、所々歪んで列を成す机も違った意味を齎す。
存在する音は遠くから聞こえてくる吹奏楽部と運動部の無秩序な練習の音だけ。
有機物のない無機的な空間は私を深く落ち着かせる。
人の気配がない場所は安心できる。
気味が悪い、という人もいるけれど、私は昼間の学校の方が気味が悪い。
同じ制服で狭い教室に押し込められて、動物園みたい。
人として扱われていないような気分になる。
夜の学校の方がよっぽど自由で健全だと思う。
私は名残を惜しみつつ、ドアの傍の机を撫でて教室を出た。完全に日が落ちきる前には帰らなければ。
私にとって丁度いい薄暗さの廊下を歩いていると、急に水音がして私は酷く驚いた。
誰も居ないと思ってたから。
足音を殺して用心深く距離を稼ぐと、水飲み場の前に立っているのが学ランを身に纏った生徒だということが見て取れた。私はほっとして足音を殺すのを止めた。
反対に私の足音に今度はその生徒が振り返る。
私は再度びっくりする。
君だった。
一瞬だけ私を見て、すぐにまた眉間に皺を寄せてぷいっと顔を反らす。水を含むと口をすすぎ、両の拳を冷やし始める。
今日だったのか。
三度目の呼び出し。
私は通り過ぎようとして、けれど気になって、結局声を掛けた。
薄暗闇の中でも彼の白い頬を汚す紅い血がはっきりと解ったのだ。
「君」
君はこっちを向いてくれたものの、睨みつける目線は相変わらずだった。
私は自分の右の頬を指差してみせる。
「気付いてる、ここ?怪我してるみたいよ、あとおでこにも血が付いてるよ」
「え?」
君が驚いてとっさに左の頬に触れる。
「違う、逆よ。ちょっと待って」
私はハンカチを取り出すと、それを濡らした。
じゃばじゃばと石造りの流しを打つ音がやけに廊下に響く。水は流しっぱなしにして、君が拳を引っ込めてしまったからだ。彼は変なものでも眺めるように、目を丸くして私を見ている。
私はついでにその蛇口も閉めると、背伸びをして君の頬と額を拭ってあげた。須釜君の横に並ぶとそれほど背が高いように見えないけれど、彼も十分この年頃の少年の中では長身だろう。
大人しく身を任せてくれたけど、不意に腹立たしげに眉を顰める。
「顔かよ。カッコワリィな。まーた寿樹になんか云われんぞ、クソッ」
叱られるのを嫌がる小さな子どもみたいな口調に私は思わず微笑んだ。
「ほっぺはほんの掠り傷よ。殆ど目立たないし、おでこはなんでもないわ。アナタの血じゃなく、相手の人の血が付いてただけみたい」
君がきょとんとした目で首を傾げた。
「お前、同じクラスの奴だよな。変な名前の」
余りに衒いのない口の利き方に私は声を上げて笑ってしまった。
君がはっとなって、しどろもどろに言葉を紡ぐ。
「あ、違う、珍しい名前の、ほら、えっと」
「いいのよ。ほんとに変な名前なんだもの」
君がほっとしたように、綺麗な目尻を緩めて笑う。こうやって向かいあって話してみると、思った以上に非常に表情のくるくると変わる子のようだ。
「お前、変、いや、おもしろい奴だな。恐くねーの、俺のこと?」
「どうして恐がるの?」
「え?だってそうなんじゃねぇ?」
君が今度は色素の薄い瞳を瞬かせる。しかめっ面の時との落差が本当に激しい。表情だけじゃなく、仕草もまだ幼くて可愛らしい。
私は血で汚れたハンカチを濯ぎながら、話し掛けた。
「確かにアナタたちにも問題はあるけどね、でも先にアナタに不愉快な言葉を投げつけたのは彼の方だったわ。その後もアナタたちが進んで喧嘩してるっていうより、向こうから喧嘩を押し売りしてるんでしょう?ただアナタの方が強いもんだから、やられた向こうが被害者みたいに映るだけで、本当はアナタたちのが被害者で加害者は向こうじゃない」
ぎゅっとハンカチを絞って、君を振り返るとずいぶんと意外なことを聴かされたって表情で私を見下ろしていた。
「結果に目を眩ませられて事実を見誤るほど愚かじゃないわ」
私が笑うと、君も笑った。
最初の日に友達に向けたふわっとした笑顔だった。
その笑顔にどうしてか胸が温かくなる。誰かの笑顔を見て嬉しくなるのなんて私は久々だった。
「俺、かなりムチャクチャにぶん殴ってきたけどいいの?セイトウボウエイってヤツ?」
「自分の身を守れるだけの能力があるのはとても良い事だと思うわ」
君がついに声を上げて笑った。
彼の外見によく似合った、高すぎでも低すぎでもない清んだ声音だった。
一頻笑って、君がきらきらと光る瞳で私の目を真っ直ぐに見た。
「なぁ、俺、。お前は?ちゃんと名前教えてよ」
今や空は完全な茜色に覆われていた。
私たちは校門のすぐ傍の花壇の脇にこっそりと座っていた。
結局私は帰りそびれてしまったのだ。それで君とこうしているのだけれど、じゃあどうして帰りそびれたのかというと、それはやっぱり君に興味があったからだろう。他の誰かなら適当な理由をつけて帰っていたと思う。
君は良く喋って、私を退屈させなかった。
彼は私の安良木という名の由来を聴きたがった。彼にとっては私の名前が珍しいものだったことも気を許してくれる一因だったに違いない。おそらく幼少時から彼が経験してきた腹立たしさを私も経験しているはずだという推測が君に同胞意識を抱かせたのだ。
生憎、私は名付け親に確固たる理由を尋ねる機会がなかった。それを告げると君は些か残念そうにしながらも、「でも、訊かねえほうがいいかもな」と云って、彼曰く人生最悪の日の経緯を語ってくれた。
私は笑うのを堪えるのに必死だった。
その私を見て君はすねたように唇を尖らせる。
「ナイショだかんな、今の話寿樹にしかしたことねーんだから」
ふふ、と指の隙間から零れる声に君は余計ふくれてしまう。本当に可愛らしい。
「須釜君とはずいぶん仲がいいのね」
「寿樹?違う違う、仲良いとかじゃねーよアイツとは。腐れ縁だよ、幼稚園から一緒な…寿樹!」
君が立ち上がって叫んだ。
私も顔を上げると校舎の方から須釜君が飄々とした足取りでやってくるところだった。彼も君同様にちょっとシャツが皺になって汚れている程度で、表面的にはどこにも怪我は見当たらない。私も立ち上がって君の後を付いて移動する。君たちを呼び出した人たちに見つからないよう、植え込みの影になっている方に隠れていたのだ。
「まったく心配したよ〜」
私たちに気が付いても足を速めたりせず、全く慌てた素振りも見せないくせにいけしゃあしゃあとそんなことを須釜君は口にする。
おおらかと呼ぶか、図太いと呼ぶかは彼に対する好意によって意見が分かれそうだ。
「教室で落ち合おうって云ってたのにさ〜戻ったら居ないんだもんね〜。まさかやられたのかと思って捜してみれば蓑本さんナンパしてるしさ〜、ハニーちゃんはしょうがない子だなぁ〜」
「ハニーちゃん?」
「ば…っ!!」
問い返す私。
真っ赤になった君。
穏やかに微笑んでいる須釜君。
「…ってっめえー!ソレで呼ぶなって云ってんだろーがぁぁっ!!」
叫ぶと同時に君の身体が踊った。
ううん、廻し蹴りって云うのかしら、私には良く解らないけれどぐるりと回転して、君の踵は須釜君の顎先を掠めていった。
須釜君が肩に掛けていた学ランがばさりとコンクリートに落ちる。
私はそれはもう、酷く驚いていた。
だっていきなり殴りあい始めたのだ、二人は。
それはとても冗談には見えなかった。
時折、殴り殴られてはぐっと呻いて息を詰める。
何なんだろう、この二人は。
止めに入ることはどう考えても危険で、私はただ目を丸くして成り行きを見守ることしか出来なかった。
君が腿を蹴られて、一瞬顔を歪める。けれど彼はその瞬間を狙い済ましていた。蹴り足を戻す動きに合わせて距離を詰め、須釜君の脇腹に拳を叩き込む。ど、っという篭った鈍い音が私の居るところまで聴こえた。
「へっ、ザマァ」
ひょこっと蹴られたほうの脚をちょっと引き摺りながら、君が数歩後ろに下がる。
肉を切らせて骨を絶つ、か。危うい子だな、と私は思った。
こほ、っと小さく咳き込みながら須釜君が殴られた辺りを擦る。
「酷いなぁ〜。可愛いのに〜。蓑本さんも思うよね〜ハニーちゃんってにぴったりだと思わない〜?」
「えっ?」
突如話を振られて私は返答に窮する。
「だから止めろっつってんだろーがぁ!何べん云やぁ解んだよテメーは!」
君がまた鋭い蹴りを放つ。それを紙一重で躱して、須釜君は自分より頭ひとつぶん低い君の髪をさらりとひと撫でした。
「なんで〜?蜂蜜みたいな髪だからハニーちゃん。いいネーミングだと思うんだけどな〜」
「最低だそんなの!それに頭撫でんなって云ってんだろ!ちょっと自分のが高いからって調子に乗るなよな!」
「ちょっとじゃないよん、11センチだよん」
「ウルセー!!」
「ああ……それでハニーちゃんか」
私の呟きに第二ラウンドに突入しようとしていた二人が動きを止める。
「素敵な色よね。私は真っ黒だから羨ましい。やっぱりご両親のどちらかが外国の血を引く方なのかしら?」
「えっ!?」
君が酷く驚いた顔で須釜君を振り返った。「僕は何にも云ってないよ〜」って須釜君が首を振る。君はまんまるにした瞳で私に視線を戻す。
「何で知ってんだよ、お前?」
「だって君、肌や瞳の色も薄いじゃない、だったら髪の色だって脱色してるんじゃないって普通は思わない?だからもしかしてそうなのかなって思っただけだけど、別にストーキングした訳じゃないんだから、そんな怯えた目で見ないでよ」
「バっ、べ、別にそんな顔してねぇよ!」
君の頬が僅かに赤くなる。
須釜君が笑ってまたぽんぽんと君の頭を叩く。
「ヒナコさんのお父さんがロシアの人だったんだよね〜。隔世遺伝では御祖父様譲りのハニーブロンドって訳。おかげで小さい頃から苛められちゃって、僕、いっつも助けてあげなくちゃいけなくてね〜。みんなが蓑本さんみたいに賢かったら楽でいいんだけど。ね〜、ハニーちゃん」
「苛められてもいねぇし、お前に助けられた覚えもねえよ!って呼ぶなっつってんだろが、このウドの大木バカ!」
結局第二ラウンドが開始されてしまった。
私は須釜君の学ランを拾い上げ、埃をはたいて、二人の気が済むのを待った。
君は真剣な顔で手を出すのに、須釜君は笑ってる。
須釜君はいつも笑っている。
君とは違い、須釜君はクラスメートに話し掛けられればちゃんと感じ良く対応していた。彼は誰とでも笑顔を交す。けれど、それは今こうして君に向けられる笑顔とは天と地ほども違う。
須釜君は君の孤立を望んでいるんじゃないかって気がしていた。
今こうしている二人を目にして、その思いが確信に変わる。
須釜君は君がわざと周囲から遠ざかるよう仕向けている。
でも、それは悪意から来るものではない。
逆だ。
好意から彼はそれを願っている。
何故ならそうすれば彼が君を独り占めできるから。
須釜君が君を大事に思う気持ちが、私には少しだけ理解できると思う。
無いものねだりの憧憬。
君は銀のナイフだ。
美しい装飾を施されたその先の刃は清らかで穢れを知らない。
刃を零すことを許すくらいなら、潔く折れる事を選ぶだろう。
穢れた私とは違う。
醜く汚れても生にしがみつく私とは哀しいぐらい異なる。
私と同じように、須釜君にも何かが在るのだろう。
なめらかな魂に憎いほど恋い焦がれて、どうか余計な傷が付かぬように護ってあげたくなる。
私と須釜君はきっとおんなじ生き物だ。
自分が大嫌いで、自分以外の誰かをこの世で一番愛してる。
他人がこんな私たちを知ったら、なんて可哀想なんだと憐れむかもしれない。けれど仕方ないのだ。私たちはきっともうそういう風にしか生きられない。
ぜえぜえと息を切らして二人が離れる。
今度は君が腹部を抑えている。
「こ、んの、根性悪が。きっちりやられたとこ、殴って、きやがって」
「だー…って、こんな可愛い顔、殴れないし〜」
「死ね!」
あははと荒い呼吸の下、須釜君が笑う。本当に楽しそうに。
その顔を見て私も嬉しくなった。
「ハニーちゃんって呼んじゃ駄目なの?私も似合うと思うんだけど」
「テメエ安良木!ふざけんな、駄目に決まってんだろ!」
両膝に手を付いて項垂れていた顔をがばっと上げて私を睨みつける。睨まれているのに、私はそんなことに必死で拘る幼さが可愛くてくすくすと笑いを零してしまう。
「あら、呼び捨てなのね。ならいいじゃない、アナタが私を呼び捨てるのを許す代わりに、私がアナタをハニーちゃんって呼ぶことを許してよ」
「駄目に決まってんだろ!」
「あはは、諦めなよ、やっぱり似合うんだよ、ハニーちゃんって。ねぇ、蓑本さん」
「うん。ぴったり」
「ぜっっっったいっ、だーめーだったらダメだっ!」
もう日が暮れてしまったというのに、しばらく私と須釜君は君をそうやってからかって遊んだ。君にとっては災難だったことだろう。
結局、私も須釜君もハニーちゃんと彼を呼ぶことを許してもらえなかった。
でも私は、私のことを呼び捨てにする代わりに、彼のこともと呼んでも云いという許可を頂けた。下の名前で呼ばれることも本来は嫌いらしく、これも限られたごく親しい人間にしか許していないという、特権のようだ。
これは結構本気で嬉しかった。
私はすでに君に好意を抱いていたから。
でもそれは恋愛感情などでは、決してない。
私は一生、誰とも恋愛なんてしない。
きっと出来ない。
だからせめて君が女の子だったら良かったのに。
そうしたら恋人の代わりに、親友になったのに。
そんなこと云ったら、きっとは怒るだろうけれど。
でも、大好きよ、。
恋人にはなれなくても、私はアナタが大好き。
例え私が遠くに離れてしまっても、アナタが倖せであることを祈るわ。
例え私がこの世から消えてしまっても、アナタのことは忘れない。
忘れないわ。
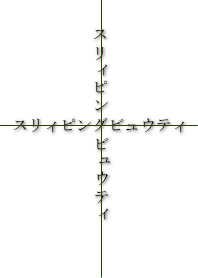
唇にキスを受けた気配がした
それは
これまで私が味わった事がないほど優しくて甘い口付けだった
|